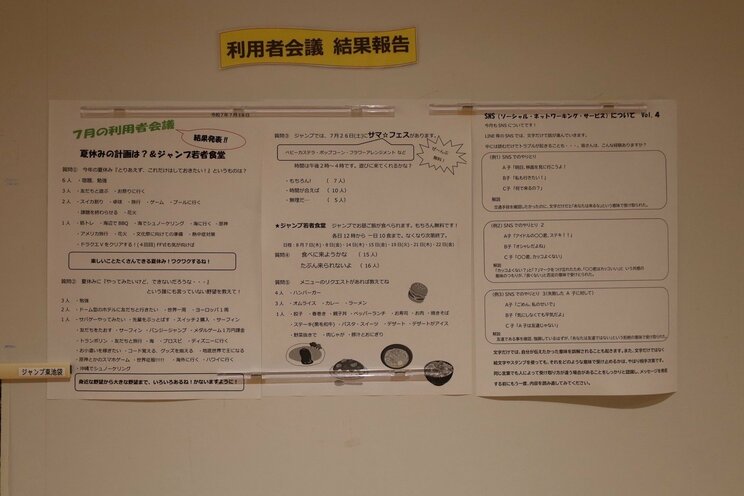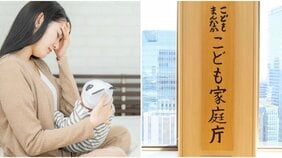「お金がかからずに遊べる場所がないという話をよく聞きます」
小さな子どもたちが遊ぶ児童館と大きく違うのはどういった点だろうか。職員は言う。
「幼い子たちですと怪我をしないようになど各部屋で職員が見守ることもありますが、ジャンプでは各部屋に職員がいて様子を見守るといったことはほとんどありません。
中高生ですので、人に迷惑をかけないなどルールを守れるようになっていることが前提でもあり、もしルールを守れない場合はその都度対応していますが、どのようにして過ごすのかは自由ですし各々の判断に任せています」
過去には家庭の事情などで家に帰りたくない中高生がジャンプに来ていて、児童相談所に連絡したケースもあったという。事情を抱える中高生たちに職員はどのように接していくのだろうか。
「仮に何か事情があるような中高生がいたとしても根掘り葉掘り聞くことは逆効果だったり、周りの人たちに自分の置かれている状況を知られたくないという思いから隠すこともあります。
また、自分がそのような状況にあると自覚していないことも。ですので、抱えてる事情について見つけることはとても難しい。
職員は中高生ひとりひとりと信頼関係を作ることを心掛けながら中高生と関わっていますので、信頼関係ができてくると会話の中で本人の方から悩みを打ち明けてくれることもあります。
それから月に一回子どもの権利擁護委員の弁護士の方に来ていただいているので、中高生はそこでも相談できます。以前に家庭に事情を抱え帰宅を望まない高校生の相談からシェアハウスを紹介してもらったり、バイトがブラックでどうすればいいか、などいろいろな相談にのってくれています」
こども家庭庁が発足されてから若者の支援について、これまでよりも国が推進しはじめたこともあり、ジャンプにも地方からの視察などが多く来るようになったという。中高生向けの児童館の必要性について職員が語る。
「近年、他県から行政の視察が増え、全国的に動きが進んでいるように感じます。それぞれ環境は違いますが、中高生向けの居場所・児童館は必要かと思います。
繁華街にはこの年代の子には魅力的に見える場所がいっぱいあるでしょうし、危険に巻き込まれることもありますからね。
中高生からお金がかからずに遊べる場所がないという話をよく聞きます。なんとなく誰かと話をしたい時、ちょっと寂しかったりする時、暇な時などどこにも居場所がないというのは中高生たちにとってつらいことだと思いますし、安全に遊べる場所として中高生向け児童館は今後もっと増える必要があるのではないかと思います」
様々な子たちの受け皿になっているジャンプ。親とも先生とも違った側面から接する“職員”という大人の存在は、心も体もグンと成長する思春期の子たちにとってきっといい影響を与えているに違いない。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班