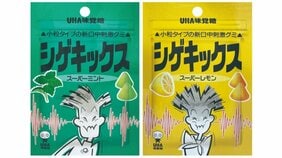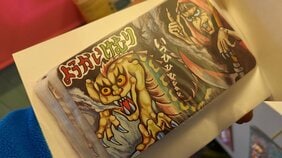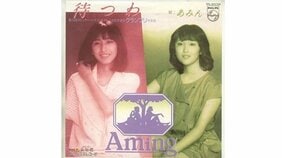ひっそりと姿を消してしまった駄菓子も
都内の駄菓子問屋に話を聞くと、「糸引き飴」終売のニュースが出た直後には一時的に注文が増加。電話の対応に追われたという。
「でも終売してしまっているから、今ある在庫でどこまで対応できるかという話になる。そんなときだけ急に販売数が増えるじゃないですか。
糸引き飴に限らず、これまで終売となった駄菓子も同じです。普段からそれくらい売れてたら、もっと商売できてたはず……という思いはありますね」
それでも、終売が話題になるだけでもまだいい。実は昨年、カラフルなフィルム包装が印象的だった「ツチタナのピースラムネ」も、メーカーの廃業により終売していた。
「地元の問屋さんにしか卸していなかったのですが、最初は1週間に100個作っていたのが、50個、10個と減っていき、終売してしまった。大きなニュースにならなかったから、気づいていない人も多いと思います」(土橋さん)
駄菓子業界を取り巻く経済状況は、かつてなく厳しい。ここ数年の物価高で原材料が高騰し、さらに包装資材や物流コストの上昇も重なって、かつての価格設定では成り立たなくなっている。
売上金額そのものは維持されているように見えても、実際には商品の単価が上がっているだけで、生産量は減少。利益も圧迫されているという。
しかし、多くのメーカーは値上げを控え、ギリギリまで努力している。そこには駄菓子屋の美学もあるという。家族経営など小規模なところでは、原材料の高騰分を自らが吸収することで値段を維持。だが、そこで立ちはだかるのが、後継者不在という問題だ。
「糸引き飴を作っていた耕生製菓さんには、手伝いが2、3人いて、基本的には熟練の職人さんがやっていました。飴の温度や、釜から上げるタイミングも感覚で判断するような、まさに“職人技”。それだけに、後継者もいなかったと聞いています」(都内の駄菓子問屋)
この問屋の主人は、ここ数年で印象的だった終売した駄菓子に、「元祖梅ジャム」をあげた。