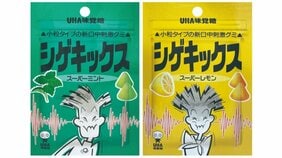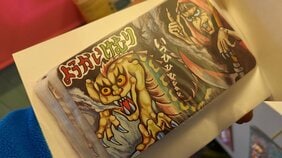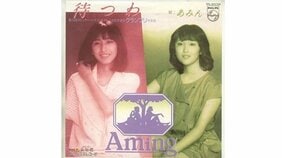駄菓子の文化をこれからも守っていくためには…
「他にも梅ジャムを作っているメーカーはありましたが、やっぱり形も味も違う。煮て作るのですが、使っていた釜が壊れてしまって、それを修理するのに400万、500万かかると言われたそうです。でも1個10円で売っていた商品のために、そこまでの設備投資はできないですよね。そうして終売してしまった。
たとえば、作っていた人が40代や50代だったら、10円の商品を15円、20円に値上げしてでも続けようと思えたかもしれません。原材料の高騰、自分の年齢のこと、後継者の問題……いろんな要因が合わさると、最終的に終売を迎えてしまう」(同)
さらに、駄菓子の売り場自体も減っている。かつてのように駄菓子屋単体で営業している店は減る一方で、クリーニング屋や文房具屋、米屋、自転車屋、高齢者福祉施設、ハンドメイドの店の一角だったりと、本業の傍らに駄菓子屋を開いていたりするケースが近年増えているという。特に、土地の高騰が進む都市部では、それが顕著だ。
また、衛生面の意識も変わった。糸引き飴のように「不特定多数が触った糸を引いて食べる」という形式は、今の衛生観念では敬遠されがちだ。着色料を気にする人も増えたという。
それでも、駄菓子問屋の主人も土橋さんも「駄菓子はすたれない」と口をそろえる。実際、今も子どもたちは喜んで駄菓子を買いに来る。そして重要なのが、大人の役割だと土橋さんは話す。
「駄菓子は子どもだけじゃなく、大人が自分のために買ってもいいのです。お酒のツマミにして、子どもの頃のことを思い出すなんて食べ方は、大人だからこそできる楽しみです。終売していくのは、いろんな事情があるから止められない部分もあるでしょう。
でも、そんなとき、後悔することなく、『ありがとう』と笑顔で送り出すためにも、普段から食べてほしいと思います」(土橋さん)
終売が相次ぐ駄菓子たち。時代が移り変わっても、この文化がいつまでも残り続けることを願っている。
取材・文/集英社オンライン編集部