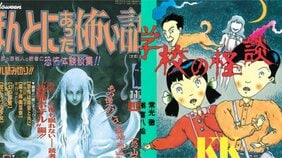「学校の怪談」のぬ~べ~オリジナル解釈
吉田悠軌(以下、吉田) 私は中学生の時、『ジャンプ』本誌で『地獄先生ぬ~べ~』(以下『ぬ~べ~』)を連載開始から毎週読んでいた世代ですので、お会いできて本当に嬉しいです。今年7月からの新アニメ化も、やはり、『ぬ~べ~』というコンテンツが求められている状況だからかと思います。それは「学校の怪談」というジャンルの再注目でもあるかもしれないし、その中で『ぬ~べ~』が代表的なコンテンツの一つとして評価されているのではないか、と。
「学校の怪談」が大ブームとなったのは90年代。90年に講談社の『学校の怪談』シリーズが刊行開始して大ヒットし、映画化・アニメ化もされる。94年には『学校のコワイうわさ 花子さんがきた‼』がフジテレビの『ポンキッキーズ』内でアニメ化、同時に書籍も含めてのメディアミックス展開をして、それも大ヒット。96年から『怪談レストラン』もベストセラーとなる。その最中の93年に『ぬ~べ~』が出てきたわけです。
当時の「学校の怪談」ブームを、お二人は意識されていたのでしょうか。『ぬ~べ~』全体は非常にバラエティ豊かな話が色々と展開していきますが、特に初期の頃は「学校怪談」路線または「学園七不思議」路線と、お二人が文庫版の解説でおっしゃっている話が多かったですよね。
真倉翔(以下、真倉) 最初は空想上の、自分たちの考えた妖怪でやろうとしていました。実際に噂になっている怪談を持ち込むというのは、当初の予定ではなかったですね。当時の『ジャンプ』ですから『幽☆遊☆白書』のようなバトルをやれ、というのが編集部の要求だったんです。大会をやって戦わせてくれ、という路線を担当からは言われていました。