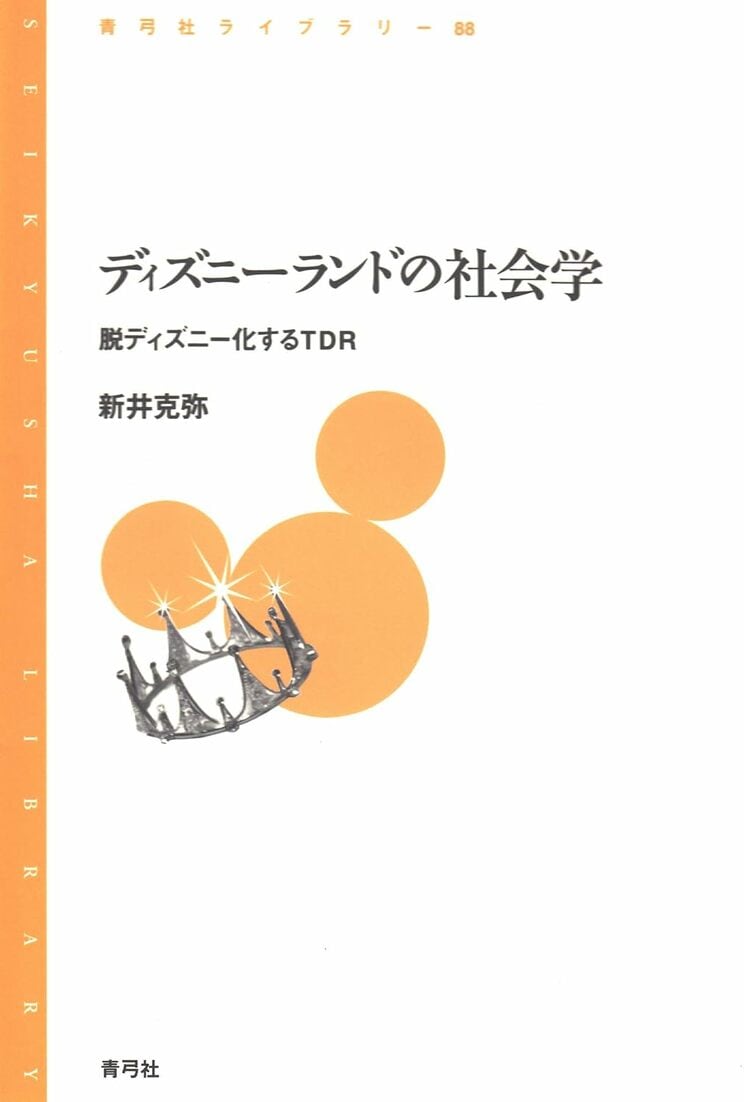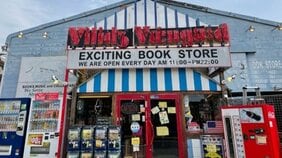「Dオタ」向けに変化したディズニーパレード
TDRはマーケティング的に変化し続けている。
ここ最近のディズニーランドの傾向だが、本来、一つのテーマで徹底的に統一されていたディズニーランドの世界観が崩されているのだ。新井克弥はこれを、ディズニーランドの「ドンキ化」と呼んでいる(ここではドンキ化という言葉は、「ごちゃごちゃした」「雑多な」という意味で使われている)。
もともと、ウォルト・ディズニーが思い描いていたパークの方向性から逸脱しているというのだ。
新井が強調するのは、ある段階までのTDRが、いわゆる「Dオタ」(ディズニーオタクの略語)が楽しめるようなパークにどんどんと変わっていった、ということ。一つの世界観を守るのではなく、色々な好みを持ったそれぞれのDオタが各自で楽しめるように、その場所が変わっていったのだ。
例えば、パレードにはその傾向が顕著に表れていると新井は言う。もともと、そのパレードは、ディズニーの世界観や物語に忠実で、そこで流れるフロート(パレードの山車とでもいうべきもの)なども計算されているものだった。
しかし、現在のパレードは、大雑把なテーマだけを決め、基本的にそこには人気のキャラクターたちが勢揃いするようになっている。それはなぜか。
Dオタたちは、ネットやSNSの情報をさまざまに調べ、それぞれが「マイ・ディズニー」ともいえるこだわりを持っている。その細分化したこだわりに対応するように、パレードのあり方も変わってきたのである。
この点でも、TDRはそこに来る顧客層を判断し、そこに特化した形での政策を行うという意味で、きわめてマーケティング的にその空間を操作しているといえるだろう。そこで、ウォルト的な「理想」はきわめて薄められる。