なぜ紫式部は漢文に通じていたのか
第一話を丸々使ってまひろの幼年時代が描かれたが、実は紫式部の前半生で明らかになっている史実はほとんどない。
その数少ないものの中でとりわけ有名なものは、『光る君へ』でも描かれた、『紫式部日記』の次のエピソードだろう。
幼かった頃、兄弟の惟規が漢籍を学んでいた。彼が理解できなかったり、覚えられなかった箇所を、私がスラスラと理解し、暗誦してしまうので、学問に熱心な父親は「もったないない。お前が男のだったら良かったものを」とよく嘆いていたものだ。
(原文)この式部の丞といふ人の、童にて書読みはべりし時、聞きならひつつ、かの人はおそう読みとり、忘るるところをも、あやしきまでぞ聡くはべりしかば、書に心入れたる親は、
「口惜しう。男子にて持たらぬこそ幸なかりけれ」
とぞつねに嘆かれはべりし。
※現代語訳は著者による意訳。原文は、宮崎莊平『新版 紫式部日記 全訳注』(講談社学術文庫、2023年)による。
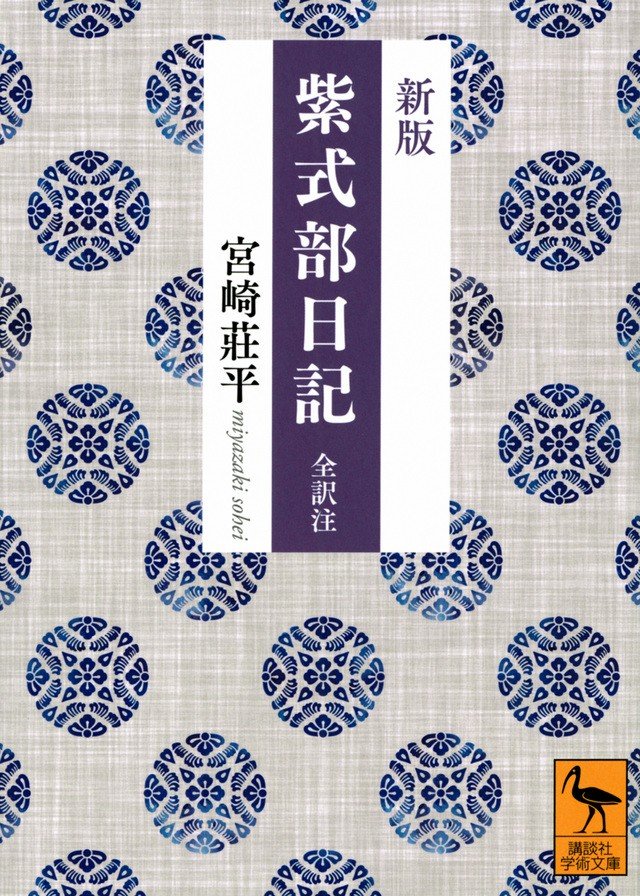
紫は幼いころから聡明だったが、当時は正統的な学問たる漢文は男性がやるものとされていたため、彼女の漢文の知識は不要なものとされていた。そのことを恥と考えた後年の紫は、自分が漢字の「一」すらも書けないフリをするなど、痛ましい努力を重ねることになる。
では、なぜ紫は漢文に通じていたのか。
それは父・為時によるところが大きい。
為時は元服後に文章生になった。文章生は現在でいうところの大学生のようなもので、漢文を学び、官僚になる準備をする。ただし大学といっても、家柄のいい真のエリートがいくようなことはほとんどなく、むしろ恵まれない家柄の者が就職するためになんとか入るような場合がほとんどだった。
そう、為時は決していい家柄ではなかった。それでも必死に漢文を学んだ結果、『本朝麗藻』という漢詩集に十三首の作品が入集されるほどになった。
だが、家柄が強くものを言う時代にあっては、それだけの漢文の知識を持ってしても重用されることはなかった。
そう考えると、為時が子供に漢文の教育を施していた思いが、そう単純なものではないことが推測されるだろう。
漢文の知識はいったいどれほど役に立つのかという懐疑がありながらも、学者として漢文を愛する気持ちは抑えられない。
『光る君へ』でも、漢文に興味を持つまひろに対して、為時が「男子だったら…」と言いつつも、うれしそうにしているのが印象深い。(このように言われた後、まひろが複雑そうな面持ちを浮かべる様子が数秒流れる。このことは後述する)





























