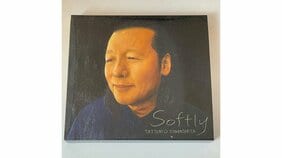日本人ラッパーがあまり書かないリリック
かなりの確率でアメリカのラッパーは、ゲットーの住人たちに共感を示す。
若くして年上の悪い男と付き合って子供ができちゃって、自分の将来を棒に振らざるを得ない女の子が子供を食べさせるために売春することになったり、仕事が無いのでドラッグを売らなきゃならなくて危険なことに巻き込まれ、死んでしまう子がいた。
「そんな無念な人生ってあるかよ!」という感情をラップしていた。
まあ、ラップに限らず、日本人はそういう歌詞をあまり書かない。日本にだっていくらでも問題はあるはずなのに。パワハラ、セクハラもあるし、いじめも虐待も慢性的にあるのに、だ。「自分はそういう境遇にいないからわからない」なんて言っていていいのか。それこそ、エンパシーが足りないんだと思う。想像できなければ、芸術家や表現者である意味がないじゃないか。
アメリカでは、日常においてはエンパシーとともにコンパッションという言葉もよく使われている。これも「思いやり」「共感力」「哀れみ」という意味の単語で、自分で体験していなくても、情熱を持って心を寄り添わせるという意味で使われている。
いいラッパーであれば「こんな可哀想な話ってないよね」「そういう悲しい現実をみんなで認識しようよ」というメッセージの歌を最低でも一つぐらいは出している。それはなぜなら自分のリスナーはどういう人たちなのかということを考え、彼ら彼女らファンたちが共感し、「自分たちのことをわかってくれてるな」と安心できるような曲を作って聴かせたいと考えるのがごく自然だからだ。
これは決してファンに対して打算的ということではなく、ファンでいてくれることへの感謝と、その気持ちへのお返しだ。歌によるコミュニケーションなのだ。