過去の優れた作品だけでも既に飽和状態
それでもハリウッドの映画産業は、投資家の顔色を見てばかりの経営陣や流動的な資本体制に支えられながら、フランチャイズ映画工場としての役割を当面は果たしていくだろう。興味深いのは、かつてユニバーサル映画やMGM映画やワーナー映画に独自の個性があったように、配信作品においてもネットフリックスやアップルTVプラスのオリジナル映画に各社の個性が見受けられるようになってきたことだ。
映画、テレビシリーズの垣根なく作家性の強い作品を供給し続けているニューヨーク(非ハリウッド)のA24のような独立系製作(及び配給、出資)会社の台頭と合わせて、「メジャースタジオ作品」の枠組や意味も時代とともに変容してきている。
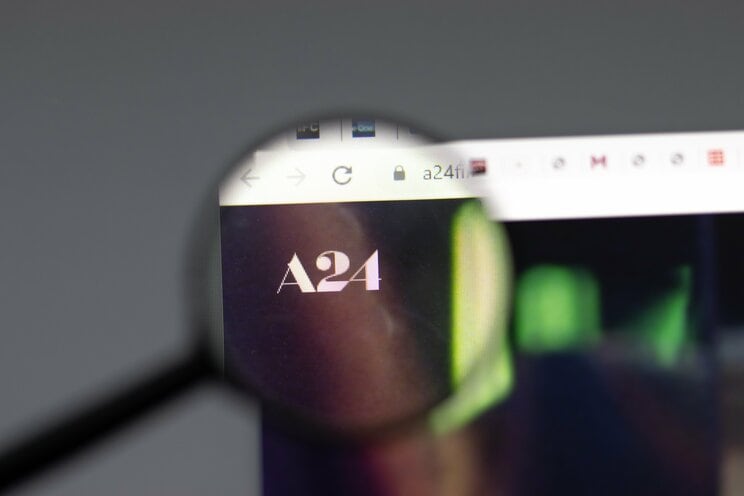
ハリウッドのメジャースタジオ作品の製作本数は不可逆的に減少し続けているが、それを補って余りありすぎるほど膨大な数の映画やテレビシリーズが、ストリーミングサービスの各プラットフォームで配信されるようになった。
観客/視聴者はストリーミングサービスで常に新作を「消化」することに追われていて、映画館でかかる新作の本数が減っていることに気づいていないか、気づいていたとしてもほとんど気に留めていないかのようだ。
一方で、特定の作品のリバイバル上映や特定の映画作家の特集上映のニーズが近年高まっている現象は、頻繁に映画館に足を運ぶ映画ファンの多くが、「新作を追う」ことよりも、過去に観た名作をもう一度スクリーンで観ることや、これまで見逃してきた旧作とスクリーンで初めて出会うことの方が、豊かで充実した映画体験への近道であることに気づき始めたことを示している。
これは、自分のようなジャーナリストも含む、新作映画に仕事として携わっている多くの映画関係者にとっては「不都合な真実」だ。長編の商業映画がコンスタントに製作されるようになってから数えても100年以上。人間が一生の間に観ることができる映画の本数の上限をふまえても、過去の優れた作品だけでとっくに飽和状態となっている。映画との付き合い方で、そこに個人の幸福の追求に重きを置くならば(つまり仕事でもなく、他者とのコミュニケーション・ツールでもないならば)、自分も中年になって以降は古い映画ばかり観る生活を送っていたかもしれない。
とりわけ現在のアメリカの映画界では、作品の主題に現代的な問題意識も必然的に流れ込んでいるとはいえ、「映画史に新しいページを書き加えてきたアメリカの映画作家たち」の多くが、特定の時代のアメリカ映画のフォルムやルックへの執着や愛着を露にするようになっている。そんな時代に、観客もまた映画を通してノスタルジーに浸るようになっていったとしても、それは無理のない話だ。
「映画館で観る映画」は、見世物小屋の催しへと原点回帰(フランチャイズ映画や低予算ホラー映画)する流れもある一方で、評価の定まっている過去の作品や名の通った監督の新作に関しては、20世紀後半にその最盛期を誇ったアートとして「美術館で鑑賞する絵画」や「オペラハウスで観劇するオペラ」のようなポジションに落ち着いていくのではないだろうか。






























