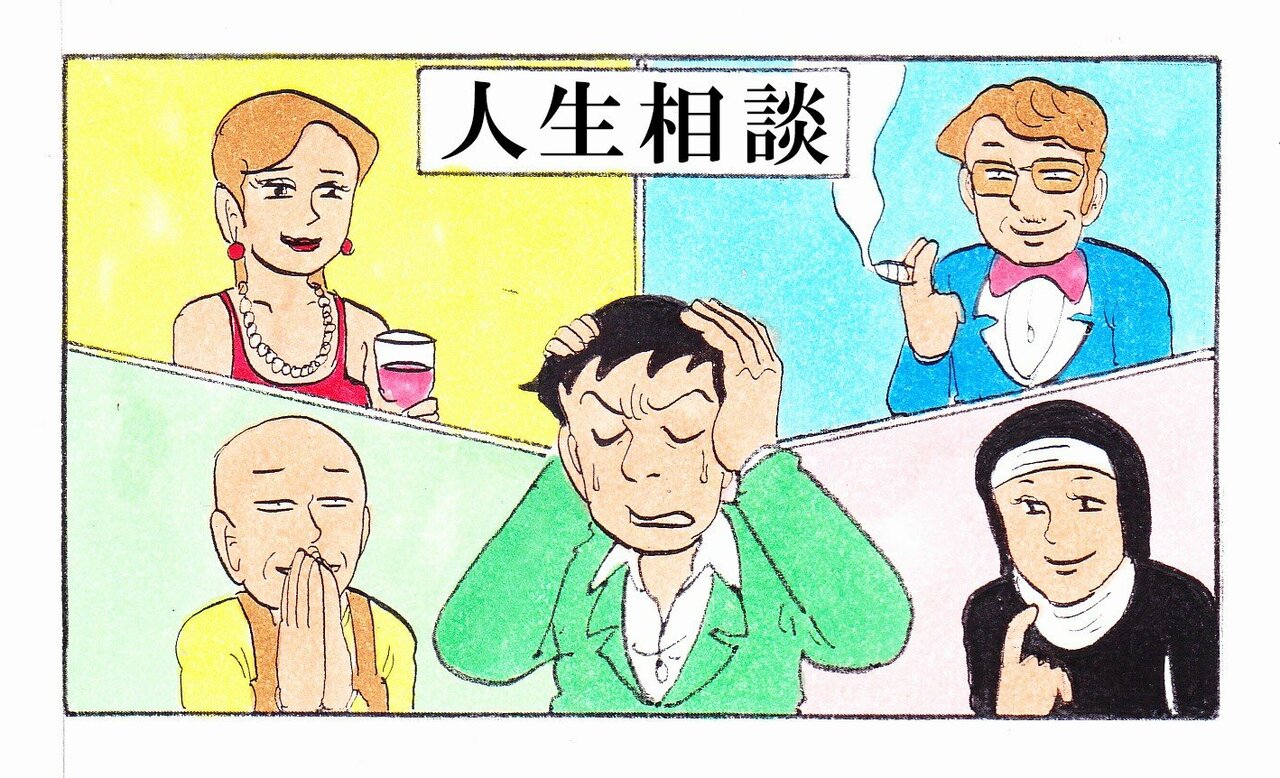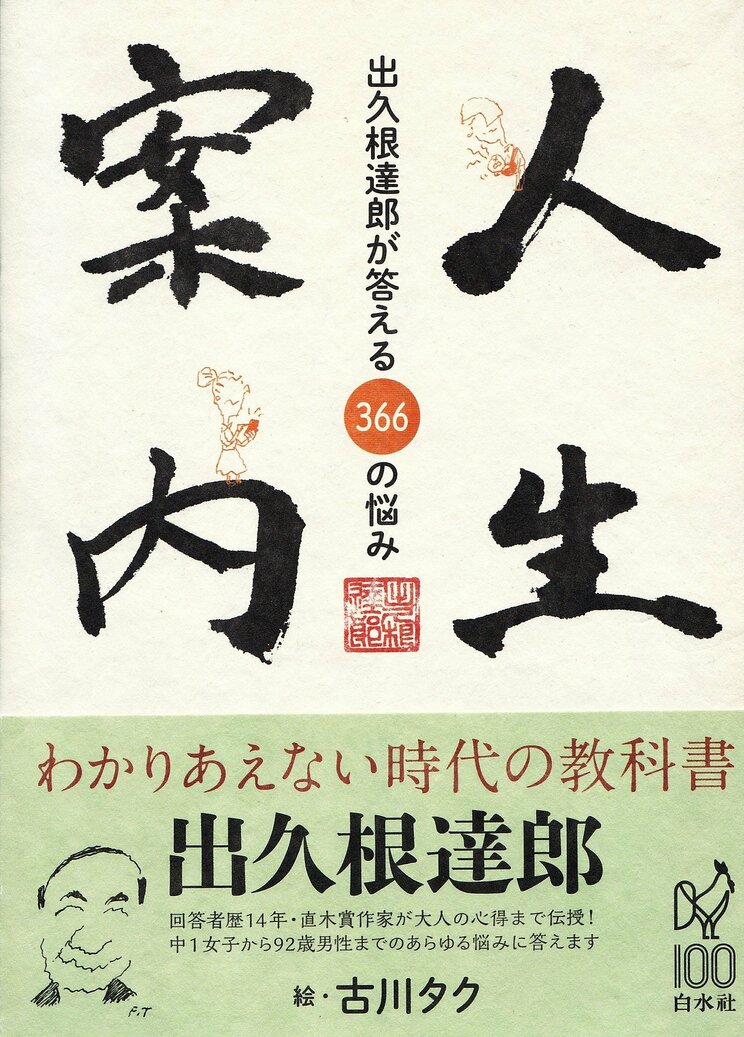「自分は被害者」と思ったときは、自分に都合良く考えていないか
1993年に『佃島ふたり書房』で直木賞を受賞した出久根達郎さん。当時は古書店の店主でもありました。以後、多くの小説やエッセイを発表しつつ、人生相談の回答者としても活躍しています。
相談者は50代の女性。長男夫婦と孫が、車で約20分のところに住んでいます。平均して週2回ほど訪ねていたところ、長男の妻に「来るときは、せめて前日に連絡してほしい。それに、週に二度も三度も来るのはつらい」と言われてしまいました。
ショックを受けて友人に話したところ「自分の娘の姑があなたみたいだったら、離婚させるわ」と言われたとか。家族だからアポなしで行くのは当然だと憤る相談者に対して、出久根さんは「私もお嫁さんやご友人と同じ意見です」と前置きしつつ、こう諭します。
〈お嫁さんの立場になって考えてみて下さい。何の予告もなしに訪ねられたら、弱ってしまいます。家族だから遠慮は無用、という考え方がおかしいので、どんな親しい仲にも、礼儀と遠慮がなくてはいけないと思います。(中略)何も来るな、と拒んでいるわけではない。あらかじめ連絡を下さい、というのですから、その通りになさったらよいでしょう。よくできたお嫁さんだと思います。こんなことで嫌ってはいけません〉
※初出:読売新聞の連載「人生案内」(2003年1月~2014年12月)。引用:出久根達郎著『人生案内‐出久根達郎が答える366の悩み』(白水社、2015年刊)
相談者の主張やお嫁さんへの憤りは、極めて自分勝手で理不尽なものにしか見えません。しかし、相談者は「実の娘のように思っていただけにショックでした」「ご近所の方は、毎日のように嫁いだ娘さん宅を訪れ、うらやましいです」などと、自分は被害者だと懸命に訴えます。
人はいかに自分に都合よく物事を解釈してしまうか、いかに他人の気持ちや迷惑を想像することが苦手か、まざまざと思い知らせてくれる事例だと言えるでしょう。