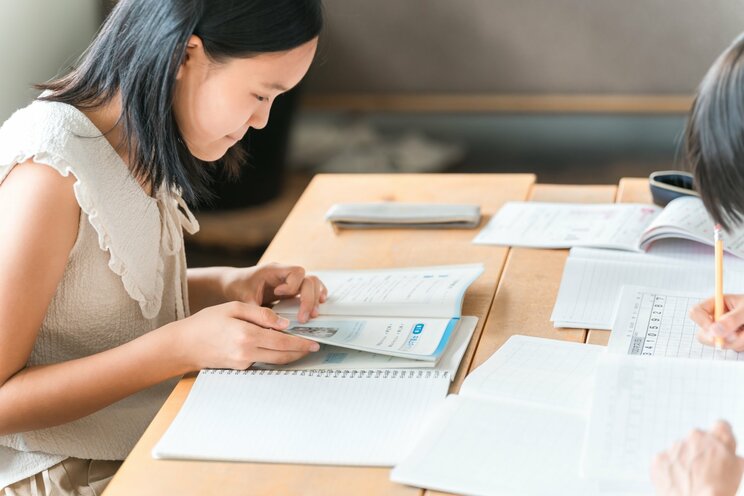「19時までを開所時間」とする東京都の新たな「認証学童クラブ事業」
そもそも、学童クラブの運営方針はどのように決められているのだろうか。東京都福祉局子供・子育て支援部の担当者に話を聞いた。
「国が示す『放課後児童クラブ運営指針』のなかで開所時間について触れています。そこでは保護者の就労時間や学校の授業の時間、地域の実情等を考慮して放課後児童クラブごとに設定する、と定められています。
また学童クラブの運営主体は区市町村とされているので、何時まで開所するかというところは区市町村の判断になります」
このように前置きした上で、都が今年度から新たに始めた「東京都認証学童クラブ事業」について担当者は次のように説明した。
「都は新たに『認証学童クラブ』という仕組みを設けました。平日は19時までを開所時間とし、さらに『19時を超えた開所に努めること』という基準を定めています。最終的に何時まで開所するかについては区市町村が決め、そこに対して利用料を取る・取らないという点についても、国の実施要項の中で『区市町村が必要な経費の一部を保護者から徴収することができる』と定めています。延長料金に関するルールは、クラブごとに変えている例は少ないと思います。区市町村単位で大体そろえているところが多いですね」
また、電車が遅延して延長料金が発生する場合については次のように話した。
「『電車が遅れた場合』という条件付きになると現場の運用の問題になり、それを形として明確に整理しているという例はあまり見ません。国の示している国の交付金と利用料徴収の考え方のなかでは、『利用料が半分・補助金が半分』となっています。
ただ実態としてそこまで保護者に負担を求められないので、安く抑えている自治体が多いと思います。だいたい月額で平均すると都内でも5~6000円くらいが多いですね」
担当者によれば、学童の開所時間拡大に関しては“悩ましい面”もあるという。
「開所時間に関しては、『保護者の利益』と『子どもの利益』がなかなか合わない部分もあります。国が定める学童クラブの運営基準では『平日1日3時間以上』とされ、あくまでも最低限の基準を定めています。
ただ、共働き世帯が増えているということを踏まえて、都が今年から始めている認証学童クラブ事業では、早くても19時までは開所していただき、その基準に沿った学童クラブについては上乗せの補助をするという方針です。
その基準を作る際に専門家の話も聞きながら進めましたが、開所時間に関しては、共働きの親にとっては便利ではありますが、子ども目線でいくと『長時間学童で過ごさないといけないの?』ということになります。さまざまな議論がありましたが、とはいえ、都市部の実情として、両親共働きで『18時までにお迎えに行く』のは物理的に難しい部分があります。学童での活動内容の充実に対しても上乗せ補助を進めていくので、子どもが楽しめるような環境づくりができればと思います」
最後に、「学童の開所時間を延ばすだけではなく、大人の働き方を変えないと根本的な解決策にはなりません」と担当者は話した。
電車遅延に伴う延長料金をめぐる取材を通して見えてきたのは、学童現場の負担、模索を続ける自治体、そして共働き世帯が抱えるジレンマだ。学童クラブ事業の持続可能性と子どもたちの「健全」な育成のために、一つずつ課題を解決していくことが求められている。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班