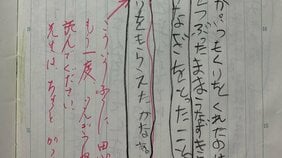「都内の学童はどこも飽和状態」
子どもが保育園から小学校に上がる際に、学校生活のサポートをすることが多くなり、仕事と子育ての両立が難しくなることを指す「小1の壁」。共働き家庭や一人親家庭で多く発生する社会的な問題である。
神奈川県の公立小学校教諭Aさん(30代男性)は「子育てと仕事の両立が難しいことは重々理解している」と前置きしつつ、現状をこのように話した。
「保護者の中には、『仕事で忙しい』というのを理由に、学校に対して協力的でない方もいます。教員の立場で言うと、持ち物の準備や宿題など家庭ですべき最低限のことは保護者の方にしっかりとお願いしたいです。
毎日の積み重ねが子どもの成長に大きく影響すると思うので、低学年の子どもには家庭でも自分で準備や宿題などができるようになるための支援をしてあげてほしいです」
では、実際に新年度がはじまり、「小1の壁」に直面する保護者たちには、どのような悩みがあるのだろうか?
30代事務職の女性(小1女児の母)はこう話す。
「近所に私の母が住んでいるから、放課後は娘を預かってもらうことができるけど、近所に身内が住んでいない家庭はすごく大変そう。今の時代、地域で一丸となって子どもたちを見守るような文化はないですし、『学童(放課後児童クラブ)に入れるしか手段がない』と話すママ友も多いです」
一方で、「常にワンオペで子育てをしている」と話す40代自営業、シングルマザーの女性(小1男児の母)は学童についてこう話す。
「最近は学童を利用する共働き家庭や一人親家庭が増えてきているため、抽選に落ちてしまい、利用できないケースも少なくないようです。私が住む区では、シングルマザーの家庭は優先的に学童を利用することができるので助かりました。
でも、都内の学童ってどこもパンパンの飽和状態で、指導員の目も届かず子どもが楽しく過ごせる環境ではないですね」