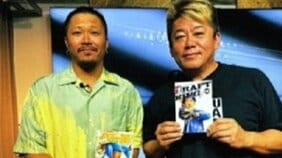共産党「東大細胞」から新聞社へ
若手記者時代にフィクサーになる
マスコミは行政・立法・司法に次ぐ「第4の権力」とも言われる。本来、権力を監視し、国民の知る権利を守るのが役割だが、どんなニュースをどう伝えるかで、世論を誘導する力がある。また、報じ方次第で政治家や企業を社会的に葬ることもできる。
大手報道機関の首脳陣にはそれだけの力があるのだが、中でも政界で大物フィクサーとして活躍した人物がいる。日本有数の巨大メディア・読売グループを率いた渡邉恒雄だ。「ナベツネ」と称されるほど世間に知られたのは、「読売ジャイアンツ」元オーナーとしての発言、そして故・中曽根康弘元首相との盟友関係によってであろう。
1982(昭和57)年から1987(昭和62)年までの中曽根政権時代、渡邉は首相のご意見番として大きな影響力を誇った。首相に直接意見できる立場から、政界の調整役としても大きな権限を振るった。その政界の黒幕としての存在感は突出しており、中曽根政権以降も政局を左右する仕掛け人として、ことあるごとにその名前が浮上した。
だが、渡邉の面白いところは、単に新聞記者として出世し、読売新聞のトップになったことをきっかけに政界フィクサー的な存在になったわけではないことだ。彼はずっと以前、若手政治部記者の頃から有力政治家に張り付き、陰でその手足となってさまざまな調整で動いた。
つまり、若手の頃からフィクサー的な活動をしており、逆にそうして日本政界の「中の人」になったことで、政治記者として情報通となり、読売新聞社内で出世していったのだ。記者がフィクサーになったというより、フィクサーが巨大メディアのトップになったのが、渡邉の特異性と言っていいだろう。
政治記者が担当する政治家と懇意になること自体は珍しくないが、渡邉の稀有な点は、その政治家と組んだ裏の動きの生々しさにある。その過程で、たとえば児玉誉士夫など裏紳士たちとの接点も濃密なものだった。そこまで暗部に踏み込める政治記者はそういない。
渡邉は1926(大正15)年、東京生まれ。東京帝国大学在学中に終戦を迎えている。戦後、日本共産党に入党し、「東大細胞」のキャップとなるが、やがて離脱し、卒業後に読売新聞社に入社した。なお、大学時代に同じく東大細胞にいたのが、後に日本テレビのトップとなる氏家齊一郎や、セゾングループ会長となる堤清二らだ。
特に氏家は高校時代から渡邉の盟友(渡邉が1学年先輩)で、共産党入党や離脱も一緒なら、大学卒業後に同じく読売新聞社に入社している。まさに、コンビとして戦後日本の報道界を渡り歩いてきたと言っていいだろう。