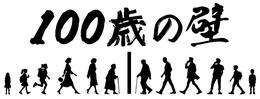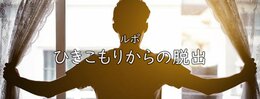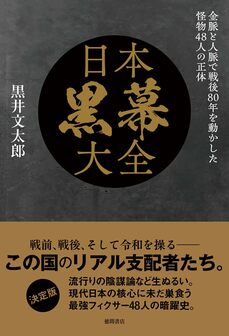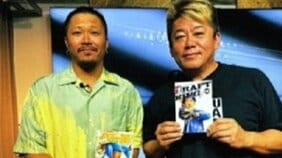党人派の周辺に蠢く怪紳士とも
読売新聞の政治記者となった渡邉は、やがて自民党の党人派の大物、大野伴睦の番記者となる。これが後の人生を決定づけた。大野は清濁併せ吞むタイプが主流の党人派の中でも、最もその傾向が顕著な人物だった。義理人情に篤いがゆえに、裏社会とも堂々と交際し(当時は問題となることはなかった)、選挙のたびに裏金が飛び交う当時の政界で重きをなした派閥領袖だった。
渡邉はそんな大野に食い込み、番記者でありながら事実上の秘書のような役割を果たすようになる。大野の雑誌寄稿文や回想録のゴーストライターを務めたほか、組閣時の大野派議員のポスト配分要求などで助言したり、さらには大野の代理として他派閥とポスト配分を交渉することすらあった。当時、大野は渡邉と2人だけで密談する様子をしばしば目撃されている。それだけ強い信頼を獲得していたわけだ。
渡邉は明らかに番記者の領分を越え、大野派の政界活動を支える〝大野親分の名代〞のように振る舞った。自民党党人派の周辺で蠢く怪しい紳士たちとも交流したが、その中には前述した大物右翼の児玉誉士夫などもいた。渡邉は児玉らとともに60年代の九頭竜ダム汚職事件や日韓国交正常化交渉でも自民党党人派の名代として水面下で動いたと見られる。
当時の渡邉は40歳そこそこという大手新聞社では中堅どころの年齢だったが、そうした立場から生情報を常に入手しており、紙面でも政界スクープをいくつもモノにした。渡邉にとっては、政界フィクサー的な動きも、特大スクープを狙う職務の手段だったということなのだろう。
渡邉が大野の名代的なポジションで動いていた時に、親交を深めたのが中曽根康弘だ。もともと渡邉は昭和50年代、読売グループの当時の総帥だった正力松太郎の命令で中曽根と会った。意気投合した渡邉は、入閣を狙う中曽根と大野の橋渡しを行い、以後、2人は固く結ばれることとなった。
その後、渡邉は中曽根が自民党内で影響力を強めたことで、フィクサー的な発言力をますます高めていった。読売新聞社内でも敏腕政治記者としての立場を確立し、ワシントン支局長、編集局参与、解説部長、政治部長兼局次長、局長待遇編集局総務と順調に出世。
1979(昭和54)年には取締役論説委員長に就任し、論調を主導する立場になった。以降、読売新聞自体が同社内での渡邉の影響力により、中曽根を筆頭とする自民党タカ派の代理人的な立場に変貌したと言える。渡邉はその後も、中曽根政権末期に筆頭副社長、1991(平成3)年に社長に就任し、それから長期にわたって同社を率いていったが、経営だけに専念せず、論調に口出しを続けた。
読売は渡邉の指揮下で、憲法改正キャンペーンなどを精力的に展開。2005(平成17)年、渡邉は読売新聞グループ本社の会長に就任しており、その頃には政界の古参フィクサーとして圧倒的な影響力を持ち、政局を左右するまでに至った。
2007(平成19)年に自民党・福田康夫政権と民主党・小沢一郎代表が進めた大連立構想が頓挫した際には、渡邉が同構想を仕掛けた張本人とも言われた。2016(平成28)年、読売新聞グループ本社会長を退いたが、読売新聞グループ本社代表取締役主筆には留まった。2024(令和6)年12月19日、読売新聞グループ本社主筆のまま病没。享年98だった。
文/黒井文太郎