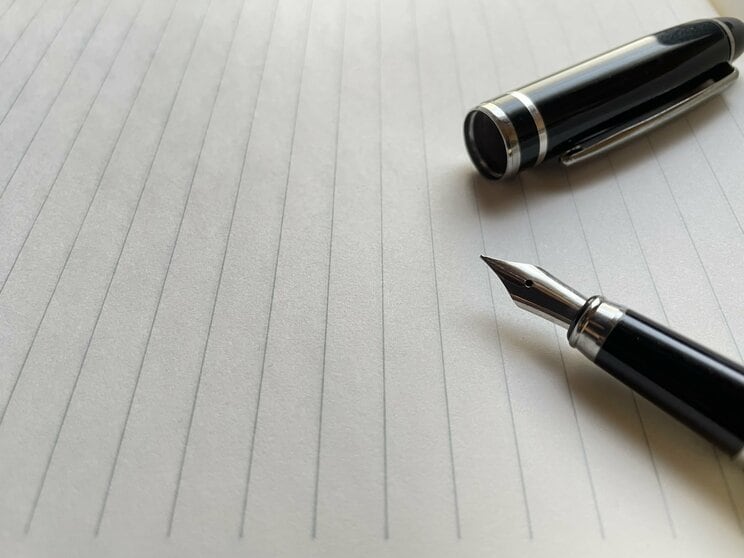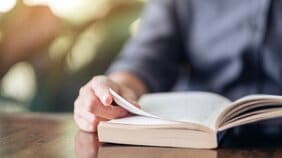本書には、松本清張作品のストーリーやトリック、犯人等が記されている箇所があります。ご了承の上、お読みください。
負けじ魂を自身に重ねた?
両親共に他界した後に清張が「婦人公論臨時増刊『人生特集』」(昭和三十七年四月)に発表したエッセイ「実感的人生論」には、女性誌ということもあり、母についての記述も多い。
そこには、
「私はこの母からかなり性格を受継いでいると思う」
とあった。
父のせいで、多くの苦労を重ねた母。生活が苦しい時は、隣家で女中として働くという屈辱にも耐えた。しかしどんな貧乏の中でも母は、清張の着物と、自分の外出着だけは、あらゆる倹約をして作っていたのだそう。
「その外出着一枚を持っているということがいつも母に人間的な矜持を持たせ、そのことによって転落して行きそうな自分を抑止していたのではないかと思う」
と、清張は書く。
母はまた、気が強い人であった。読み書きができないからこそ馬鹿にされないようにしていたという面もあれど、その負けん気を発揮するのは、他人から理不尽なことをされた時だった、とも。
清張もまた、負けじ魂の強い人である。清張作品の中には、大学教授の世界の欺瞞を描く小説がしばしば見られるが、それは高等小学校卒という学歴のせいで、会社勤めをしていた時代も理不尽な思いを重ねた清張が、大学という権威に放つ矢のようなものだったのではないか。
「婦人公論臨時増刊『人生読本』」(昭和三十三年九月)に寄せたエッセイ「学歴の克服」には、大卒でないことへの劣等感や、学歴がない故に受けた差別待遇について書かれている。
しかし学歴はその後の勉強次第でどうとでもなるのであり、
「人生には卒業学校名の記入欄はないのである」
とこのエッセイが締めくくられる。
考古学や語学等、清張が独学で勉強を重ねたのは、まさに学歴を克服するためでもあったのだろう。その時に清張は、読み書きができないながらも、ふりかかった火の粉を振り払いつつ相手に果敢に立ち向かう母の姿を、自らに重ねてはいなかったか。
清張は、男性作家がしばしば書く、母への手放しの賞賛や愛を、エッセイには書いていない。清張が母への愛を記しているのは、むしろ小説においてである。
清張が芥川賞を受賞した最初期の短編「或る『小倉日記』伝」は、実話に基づいた、不遇の母と息子の物語である。
身体に障害を持つ息子の才能を信じ、献身的に彼の研究を支え続ける母の美しくも悲しい姿が、そこには描かれる。しかしいかにも清張らしい母親像は、むしろ同年に書かれた短編「火の記憶」に現れているように私は思う。