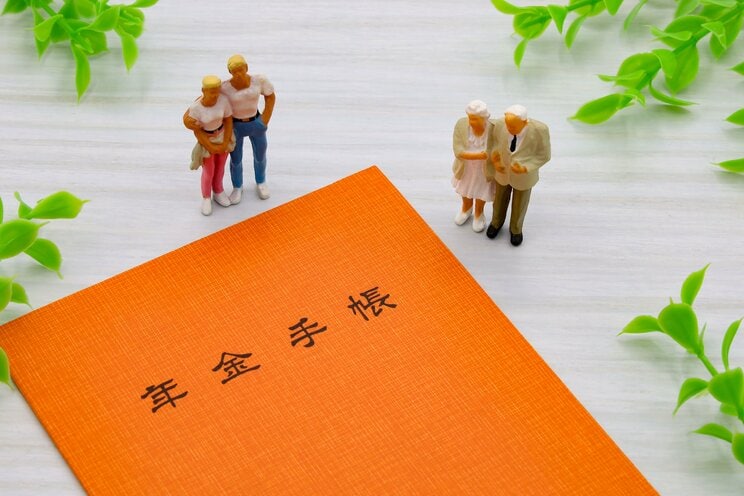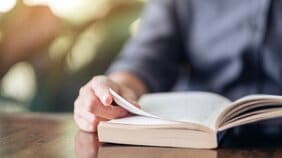娘を結婚させることをしばしば「片付ける」と表現した時代
また短編「年下の男」の主人公である加津子は、電話交換手として新聞社に勤める35歳。18歳で就職し、結婚しないまま17年間、仕事を続けている。
彼女は30歳が近くなった頃には、すでに、結婚を諦めていた。頼ることができるのはお金だけ、とせっせと貯蓄に励んでいたのだが、ふとしたことから年下の恋人ができる。しかし、やがて彼が若い女と遊ぶようになったのを知った時、彼女は彼を……。
両作品が発表された1960年代、女性の平均初婚年齢は24歳台であり、20代前半で結婚する人が多かったものと思われる。
独身女性は26歳にもなると「後妻の話」が来かねなかったり、20代末期でもう結婚を諦めたりしていたのだ。
清張が男性であることを考えると、清張の個人的感覚として「二十五歳を過ぎた独身の女」に対して、ことさら「薹(とう)が立った」感を持っていたのかもしれないが、いずれにしても独身女性にとって25歳は、深刻な意味を持つ年齢だったのだ。
今であれば、20代後半の女性が独身でも、何ら不思議ではない。令和5年(2023)時点での女性の平均初婚年齢は29.7歳であり、昨今の女性たちは、60年前の女性が結婚を諦める年頃になって、ようやく結婚していく。
60年代は、女性は就職しても、結婚したら退職する人が大多数だった。30歳を過ぎて勤め続けても、『黒革の手帖』の元子のように出世は望めず、仕事のやり甲斐も感じられず、“職場の花”としての価値は暴落し、どんどん居づらくなっていったのである。
となると実質的に、女性が一生食べていく方法は、ほぼ結婚に絞られていた。昭和40年(1965)には、「夫婦のうち一方が働き、子どもが2人いる4人世帯」を「標準世帯」とした年金制度ができている。
男性が外で働き、女性が主婦としてそれを支えるという家族モデルを国も推進していたのであり、若い女性は生鮮食品かのように、早めに出荷されたのだ。
当時の親たちは、
「うちの娘も二十四、早く片付けなくては」
「娘がやっと片付いて、肩の荷がおりました」
などと、娘を結婚させることをしばしば「片付ける」と表現していたが、独身の娘という腐りやすい存在を、適当な時期に結婚させなければならないというプレッシャーが、その言い方からは感じられよう。