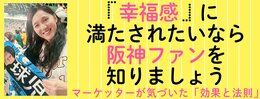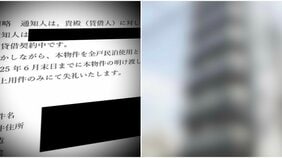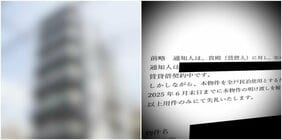森林や水源地や農地なども
さらに脅威に思うのは森林や水源地や農地などの日本の重要な資源を有する地域までが買い漁られていることだ。先祖代々守られてきた田舎の山林なども、核家族化が進んで都会暮らししている世代にしてみれば、相続したところで持っていても税金ばかり取られるばかりか、資産価値はほとんどないと考えているはずだ。
そこへ、中国人投資家が相場の数倍で買うということになれば、ホイホイと売ってしまう。実際に2023年までのデータでも外国人の森林取得事例は358件、2868ヘクタールにも及んでいて、この2年でもかなりのスピードで進んでいる。
我々の気が付いていない間に山の手線の内側の約半分、渋谷区の2倍もの土地が彼らの手に渡っているのである。
山林が外国人の手に渡った場合、最も深刻なのは「水」であろうと思う。水は人間が生きてく上で最も大切な資源であるのは言うまでもない。山林は水源涵養機能を持ち、降水を一時的に貯留し、河川への流量を平準化する役割を果たしている。 そのため、山林の管理は水資源の保全に直結するのだ。
2050年までに、世界人口の約半数が慢性的な水不足にさらされると予測
だから山林がいたずらに彼らに渡れば、そこに含まれる水源地にも及び、地域の水資源への影響が大いに懸念される。よく日本人は近視眼的なものの見方をし、大陸の人間は何十年先も見据えたものの見方をするというが、まさにその通りなのだと思う。
水を取り巻く現状を見ると世界人口の約50%に当たる約40億人が、少なくとも年に1か月は水不足に直面しており、2050年までに、世界人口の約半数が慢性的な水不足にさらされると予測されている。
特に待ったなしの死活問題になっているのがインドだ。インドは2025年度末までに名目GDPで日本を上回り、世界第4位の経済大国になるとIMFが予想しているが、過去10年間で何と名目GDPを2倍以上に拡大するほどの急成長を遂げている。
そのインドの人口の約80%が地下水を飲料水として利用しているのだが、過剰な汲み上げにより地下水位が急速に低下してるそうだ。 このままでは2030年までに人口の約40%が飲料水を入手できなくなると予測されている。
特にニューデリー、ムンバイ、ベンガルールなどの都市部では、大規模な開発と人口増加によって、一気に水の需要が急増し、供給が追いついていないという。 例えば、南部の都市チェンナイでは主要な貯水池が干上がってしまっていて、深刻な水不足に陥っているそうだ。