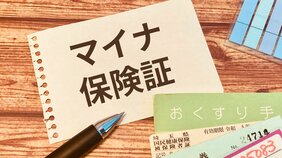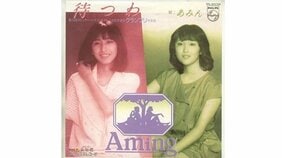運営が難しい「健康保険」はマイナ一体型が理想
「健康保険制度」は、年金制度以上に運営が難しいし、多くの課題がある。
年金は人口減少など予測可能な要因が多く、大きな戦争や巨大な自然災害でもない限り、年金数理をもとに将来の年金支給額を計算しやすい。
しかし、健康保険は10年後、20年後の医療費の総額がいくらになるか、という予測がしづらい。将来、また新型コロナウイルスのようなパンデミックがまん延するかもしれないため、先読みがしづらく、治療費の不透明さがあるからだ。
医療の進歩により、新しい治療法や薬が開発される一方で、治療費の高額化も懸念される。すでに数百万円かかる高度な治療も存在している。
こうしたことから、年金よりも医療費のほうが予測しづらいのだ。
医療費の一部は公的健康保険でカバーされ、それを超える高度な医療は民間医療保険でサポートされる仕組みが構築されつつある。今後は、公的健康保険と民間医療保険を使い分ける人が、目立ってくるだろう。
高齢化が進むなかで医療ニーズが増加する一方、国民が負担できる保険料には限界がある。そのため、いずれは保険対象となる医療費の総額が設定されていくだろう。医師が患者の症状を選別し、症状の重い人から優先的に、総額の範囲内で配分されるような方法が検討されていくと予想される。
健康保険制度の運営が難しいもう一つの要因は、本人確認が容易でなかったことだ。従来の保険証には顔写真がなく、他人のなりすましや不正利用、本人確認のミスがかなり発生していた。厚労省のデータによれば、年間約500万件もの再確認が必要とされ、そのコストは約1000億円に上っていたという。
健康保険証が本人確認の一環となっていた社会システムでは、人間の性善説を前提としていたため、マイナンバー保険証への移行が急がれていた。そこで、一体型の「マイナ保険証」になれば、他人によるなりすましや不正使用の問題は解決できる。
すでに紙の保険証は廃止して、マイナンバーカードに一本化する作業が進められている。岸田首相は最近、国民の不安解消を最優先に考え、現行の保険証は1年間の猶予期間を設けて引き続き利用可能とし、その間に不安を解消する方針を掲げた。