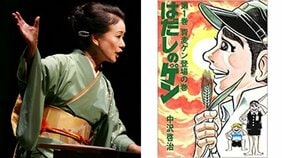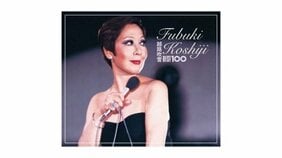「ニュースの数値化は恥ずかしい」という文化はもはや風前の灯火
一筋の希望になりえる記者たちだが、意に反して離脱するケースも少なくない。その責任感と使命感ゆえに「体を壊す」「心を壊す」、さらに「家庭を壊す」と3つのリスクを抱えていると、先輩たちの働きぶりを知る30代の明さんは指摘していた。
とりわけ米軍基地の存在が常態化し、米兵や戦闘機によるトラブルが頻繁に起こる沖縄の記者は、海外の紛争地で取材する記者と同じストレスに晒されると言われる。
広島を拠点とする小山美砂さんも毎日新聞社を退社した理由は、心のバランスを崩したことが一つのきっかけだったと語ってくれていた。
こうした何かの犠牲の上にあるのも時代錯誤である。明さんは忙しくても、家族の誕生日や行事のために休暇をとっていた。それを知って私は思わず落涙した。
沖縄戦の延長線上にある基地被害のダメージを抱えている家族をケアすることを忘れていない。忙しくても家族をケアしてやまない彼に新しい記者像を見た思いがした。
妻の有希子さんは、沖縄戦で孤児になった祖父の苦難に満ちた人生が頭から離れない。米軍に全ての家族を奪われながらも、米軍に関わる下請け仕事などで生計を立てるしかなかった祖父。
さらに自分の子どもが通う保育園の屋根に米軍機の部品が落下。危険を回避できないことに心かき乱される。世代をまたいで基地被害は続く。
戦争体験者の頭上を米軍機は飛び続け、日本政府は子どもたちを守らない。主権は米軍にあるのか。軍用機の騒音に悩まされない東京に引っ越し、小学生の娘は静かな空を見上げ、「インチキな空」と口にした。
沖縄に米軍基地を押し付けて穏やかな空が保たれている構造の「インチキ」さを見抜いたのだ。自衛隊駐屯地が去年開設された石垣島の小学生は、平和を考える授業の中で、「平和とは、公平であること」と作文した。南西諸島への自衛隊ミサイル基地のさらなる押し付けという「不公平」を言い当てたのだ。
記者がいる職場はいま、人手不足が深刻だ。忙しさのあまりアドレナリンの高まりに身をゆだねる毎日では消耗してしまう。
そうすると、スムーズに物事が運ぶことを優先して流される思考停止のパターンに陥る。問題を解決するのではなく、問題から逃れる道へと進んでいきかねない。
放送局であれば、目先の視聴率を追いかけて満足してしまう。ページビュー数を稼げたと記事を数値評価し、記者の人事評価までしてマネタイズに走る。
ニュースの数値化は恥ずかしいという文化は風前の灯火だ。命にかかわることも札束で計算してしまう。そんなビジネス論理を追求すればするほど、争いごとや戦争へ社会はじりじりと引きずり込まれるだろう。
人を殺傷する武器も魂を殺すヘイト本も稼ぐツールになるのだ。
助け合い、支え合いで成り立つ、市場の側面とは違う人間らしい理性の働く社会を劣化させるほうへ傾く鈍さに気持ちがふさぐが、怒りと悲しみでもだえそうになっても記者に希望を託し、未来への光を見出す人たちがいることも知っている。
私自身は、やり切ったのだろうかー。漫画「ベルサイユのばら」に魅了され、子ども心に働く女性に憧れた時代から半世紀余りが過ぎた。
ひとまず目標の「定年まで働く」はたどり着きそうだが、「やり切った」とも思えない。その先にはさらなる世界が待っている。
かじりついた石は、とっくに擦り減って、この手から離れていたのかもしれない。いや、確かに大きな石はあったし、今もなくなってはいない。
芯となるその石を手に持った人たちと素晴らしい出逢いを繰り返してきた。深く感謝している。それは仲間だけでなく市井の小さな声の人びとであることが多かった。
「石にかじりついてもー」、そんな気持ちにさせてくれたジャーナリズムの拠点はいつでも作れると信じている。誰一人犠牲にさせないぞと誓い、個人を大切に尊重する社会の仕組みを強固なものにしてゆきたい。
文/斉加尚代