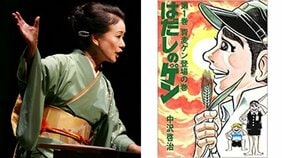偽の「中立神話」の弊害
TVerでも全国配信された番組だったが、防衛省担当の記者たちは、明さんに対し正面切って何も言わなかったという。
酒席で言ってきた記憶もない。意外にも現場を知る自衛官たちは、知らせてもいないのに明さんにいろいろ感想を述べてきたそうだ。
琉球新報は防衛政策に厳しい論陣を張る。明さんが執筆する記事も批判的なものがほとんどだ。それでも人間同士やり取りができる。
立場は違えど芯があるからこそ信頼しあえるのだろう。これが本来の記者の姿ではないだろうか。
権力におもねる記者たちは職責を忘れていると言わざるを得ない。いずこもクラブに常駐する記者たちは統制される危険と隣り合わせだ。
あの日から「泥水につかりながら染まらないようにしている」と語っていた明さんの真意を理解し、記者が記者であり続けることにも特別な踏ん張りが必要なのだと痛感するのだった。
最近、「ニュースなんて見たくない」という声もよく聞く。現実を直視して暗い気持ちになりたくない心理的傾向とシンクロする。
確かにむごたらしい戦争には目を覆いたくなる。時代に斬りこむジャーナリズムは、強く闘える者たちの世界と感じることすらある。
だが、暮らしの中で苦しんでいる当事者たちは、現実を違った角度から直視することで「癒し」を得られるという。ドキュメンタリー制作を通して教えられたことだ。
差別やヘイトを正面から問題視する言論によって「すっきりする」「癒される」と語る人たちがいる。
当初、崖っぷちに立つ当事者が語るこの「癒される」という感覚が分からなかった。他者から提示されることで、自身のもやもやが少し晴れ、心の居場所が見つかるというのだ。
私がおもに取材してきた教育現場でも同様に、苦しみの原因が露わに描かれることで回復に向けた希望を感じる、あるいは勇気をもらえたと語る人たちが多くいる。
考えてみれば、見たくないと回避できるのは、無関心でいられる層である。その無関心な人びとの想像力にどう働きかけるかがメディアに問われている課題だろう。
極めて残念なのは、この国は実のある主権者教育をせずにきた。ある意味、社会や政治に対し無関心を是としてきた。政治的中立性とは、政治にモノを言わないことだと信じこまされている。
公立学校で教員たちが自由に意見する土壌も薄れている。記者も教員も「中立神話」の空気に覆われる、その偽の「中立」の弊害が見過ごせない。
黙らずに、正当に意見表明しただけで文書訓告の処分が下されるという事態すらある。大阪市立小学校元校長の久保敬さんは、外国特派員協会(FCCJ)の会見(https://www.youtube.com/watch?v=sA4RLHZgHDo)で、「モノを言わない」「黙って従う」ことが現代版の愛国教育だと警鐘を鳴らした。
偽物の「中立」に捉われるあまり、社会を語らない社会科教員が登場していると聞く。自分たちが社会の一員であり、社会を変えていく主体なのだという意識が持てないのだ。
政治不信が高まっても、その政治にNOを突きつける民意が勢いづかないのは、自分たちの主権を信じていないからではないか。