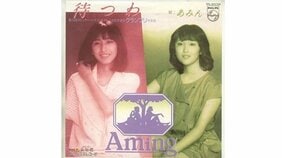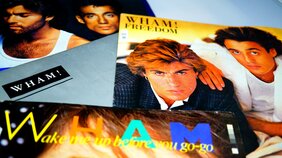日本教育の大きな岐路となった「1969年」
若者の政治参加の低迷、「ブラック校則」や「部活動強制加入」を考えるにあたって、「1969年」ほど重要な年はない。「1969年」は、戦後目指してきた日本の民主化教育を諦め、管理教育へと大きくシフトした象徴的な年だからである。
その最大の象徴が、主権者教育に関心のある人々の間では有名な、「1969年通達」である。
昭和44年(1969年)、文部省は「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(昭和44年10月31日文部省初等中等教育局長通知)という通知を出し、高校生の政治活動を「教育上望ましくない」とし、政治教育も慎重に行うべきだとした。
「放課後、休日等に学校外で行なわれる生徒の政治的活動は、……学校が教育上の観点から望ましくないとして生徒を指導することは当然である」
「現実の具体的な政治的事象は、取り扱い上慎重を期さなければならない性格のものであるので、必要がある場合には、校長を中心に学校としての指導方針を確立すること」
通知の背景にあったのは、東西冷戦の激化、60年安保闘争の激化、学園紛争の激化である。
また、「部活動強制加入」につながる「必修クラブ」が導入されたのも1969年である。1969年、1970年改訂の学習指導要領において、任意の自由研究の一環として導入された「クラブ活動」が必修化され、1999年の見直しまで「必修クラブ」は続いた。
「クラブは、学年や学級の所属を離れて共通の興味や関心をもつ生徒をもって組織することをたてまえとし、全生徒が文化的、体育的または生産的な活動を行なうこと」(文部省1969年中学校学習指導要領)
そして部活動との代替措置が取られ、いまなお部活動の実質的必修化は色濃く残っている。
一方、戦後日本は「民主化」を目指し、「民主主義」教育を積極的に行おうとしていた。「クラブ活動」が導入された1951年学習指導要領では、特別教育活動は生徒自身の手で計画・組織・実行・評価されるもので、それを通じて民主的生活の方法を学び、公民としての資質を高めることができるものとされた。つまり、「特別教育活動」は、民主主義の原理と生活の方法を学ぶ活動として位置付けられていた。
「クラブ活動は当然生徒の団体意識を高め、やがてはそれが社会意識となり、よい公民としての資質を養うことになる。また、秩序を維持し、責任を遂行し、自己の権利を主張し、いっそう進歩的な社会をつくる能力を養うこともできる」
「生徒は強制されてはいけない。生徒がクラブ活動の中心である。したがって、クラブ組織については、生徒評議会の会議でじゅうぶん討議され、審議されるべきである。教師は指導者となって働いてもよいが、生徒の意見を重んじなければならない」(文部省1951年中学校学習指導要領)
「生徒は強制されてはいけない」「自己の権利を主張し」と、クラブ活動はあくまで、民主主義社会の形成者を育成するための取り組みだったのである。だからこそ、生徒自身の意思を尊重することを重視していたのであり、強制していては「民主化」教育につながらないと考えた。
「クラブ活動に全校生徒が参加できることは望ましいことであるが、生徒の自発的な参加によってそのような結果が生れるように指導することがたいせつである」(文部省1958年中学校学習指導要領)
しかしそうした精神は今となっては失われた。その転機となったのが、上述の1969年から始まるクラブの「必修化」である。
写真/shutterstock