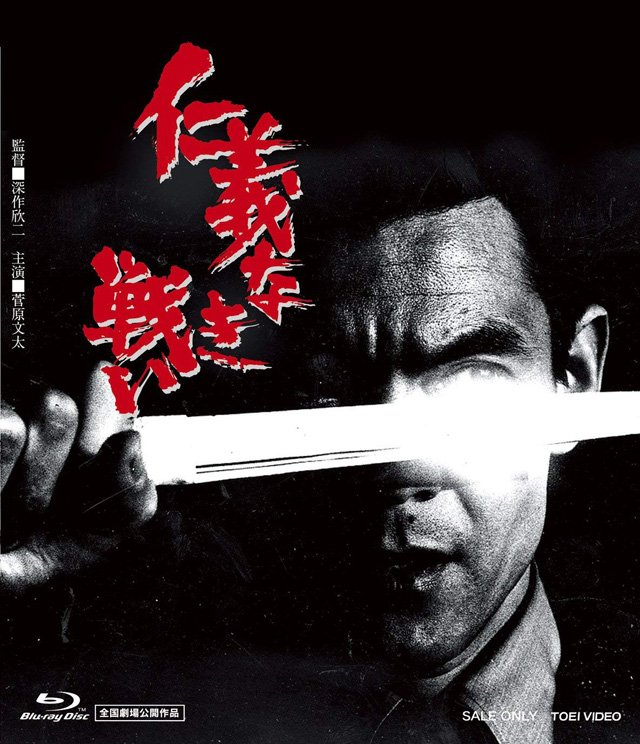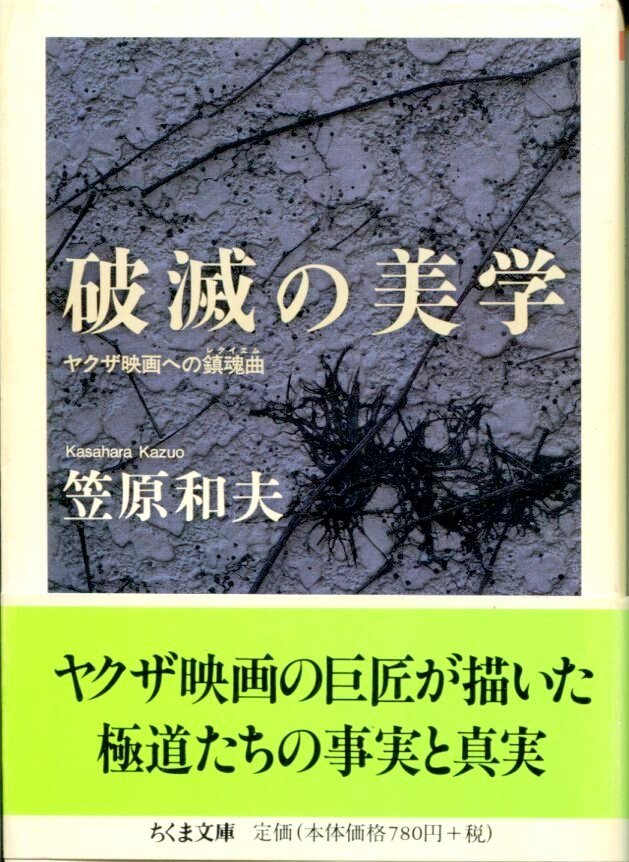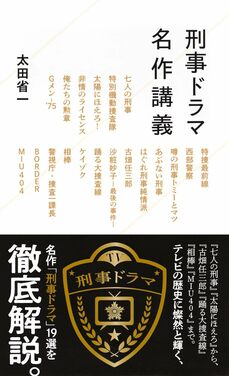『踊る大捜査線』は『仁義なき戦い』だった!?
そのようにとらえるとき、亀山千広が語る次のような回顧談は、俄然重みを帯びてくるように見える。
それは、『仁義なき戦い』という映画にかかわる話である。改めて説明の必要もないだろうが、『仁義なき戦い』は、1973年に公開された映画。広島を中心とした暴力団同士の抗争を描いたやくざ映画だ。
この作品を製作した東映は、それ以前からやくざ映画を得意としていた。ただしそこでは、やくざの世界の伝統的しきたりや仁義中心の価値観を援用しながら、いわゆる「男の美学」が一種の様式美として描かれていた。要するに、理想化された世界である。
だが『仁義なき戦い』はまったく異なっていた。実際にあったやくざ同士の抗争を記録したものを原作に、やくざの世界を泥臭く、そして生々しくリアルに描いた。
監督である深作欣二の手持ちカメラを使ったダイナミックな撮影も効果的で、『仁義なき戦い』は「実録もの」と称されて予想外の大ヒットとなり、すぐさまシリーズ化された。
ではその『仁義なき戦い』が『踊る大捜査線』とどのようにかかわっていたのか?
プロデューサーの亀山千広が組織論の観点から『踊る大捜査線』をつくるというアイデアを抱いたことは前に述べた。そして当然、その話を脚本の君塚良一にもした。
すると君塚は、『仁義なき戦い』の脚本家である笠原和夫の本を持ち出してきて、それは『仁義なき戦い』ではないかという話をし始めた(前掲『キネマ旬報』、64頁)。
『仁義なき戦い』は、血で血を洗う抗争を描いたやくざ映画のイメージ。一見的外れに思うかもしれない。だが君塚にとってはそうではなかった。
たとえば、シリーズ第3作の『仁義なき戦い 代理戦争』(1973年公開)などは、単純な暴力沙汰よりも、あの手この手を使って相手、場合によっては身内すら出し抜き、騙してでも組織を守り抜こうとするやくざの涙ぐましいまでの努力が滑稽なまでに戯画化されて描かれている。
その様子は、対極にあると思われている警察でも変わらないのではないか。そう君塚は考えたのである。この経緯を踏まえ、亀山はこう語る。「つまり『踊る』は僕らの中で、半分『仁義なき戦い』なんですよ」(同誌、64頁)。
『仁義なき戦い 代理戦争』は、1960年代初頭の話である。終戦からある程度時間が経ち、経済も上向いて世の中が落ち着いた頃のことだ。
混乱期が過ぎ、一般企業と同様にやくざも組織化が進む時代のなかで、当時の米ソ対立と同じく武力を背景にした外交戦術の巧拙が問われるようになる。要するに、やくざの世界も社会全般と変わらないものになったのである。
笠原和夫は著書のなかでこう記す。「戦後、民主主義の普及と産業の変革によって、徒弟制度や部屋制度の不文律社会が崩壊し、それに伴って、〈仁義〉なき戦いが始まった。それはいまもあらゆる階層に及んで拡大しつつある」(笠原和夫『破滅の美学』、322頁)。むろん警察にもまた水面下での派閥争いがあり、組織のなかでの激しい駆け引きが存在する。
それはきっと、だいぶ以前からあったものだろう。だが1990年代後半になってようやく、刑事ドラマはそのリアルな現実を、シニカルな視点を交えながら俎上に載せることができるようになった。
『踊る大捜査線』は、「様式美」に傾きがちだった刑事ドラマを「実録もの」という新たなエンタメに変えたのである。
これ以降、刑事ドラマはそこから後戻りすることはできなくなった。
文/太田省一