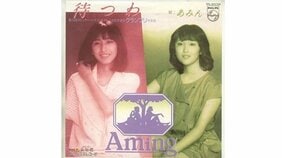大学や学部によっては入学者の3割以上が中退している例
トロウ・モデルは、大学教職員に意識改革を迫るものでもあります。
たとえば現在、大学に進学してから中退する学生は少なくありません。大学や学部によっては入学者の3割以上が中退している例もあります。大学を取り巻く環境が変わり、それまでとは異なる層の学生を受け入れているのですから、入試広報や入学前教育、初年次教育などのあり方を従来と変えないままでいれば、中退者は増えて当然です。
これまで多くの大学は「全日制の普通科高校で学んでおり、ある程度は自学自習ができる18〜20歳程度」という入学者像を想定してきました。ですが現在は商業高校や工業高校といった専門高校、定時制や通信制高校からの進学者も増えています。
こうした学生のニーズに応え、支持される大学になることも大切でしょう。現在は発達障害のある学生など、専門的な支援や配慮が必要な学生も全国の大学で多く学んでいます。教員はもちろんですが、職員にもこうした変化への対応が求められています。

優秀な教員は他機関や海外に流出する
また一方で、教育や研究に求められる成果の水準が上がり、教員の負担が増す中で、教員と職員の役割分担や関係性が従来と同じままであるなら、教員たちはそのうち倒れてしまいます。教育・研究の水準低下にもつながりますし、優秀な教員は他機関や海外に流出するでしょう。
産学連携、地域貢献など大学に求められる役割は年々増える一方です。今後はシニア層が大学で学べるような環境やプログラムの整備も必要になってくるかもしれません。職員が担う業務は高度化、多様化していくことでしょう。
いま定年間近のベテラン職員と、30歳未満の職員とでは、生涯に経験する業務の質も量も違ってくるはずです。先輩から引き継がれた業務を真面目にこなすことは大切ですが、誰も体験していない問題の解決にあたらねばならない場面も増えていくと思われます。こうしたさまざまな変化に大学は対応できているでしょうか。いま大学で働いている職員たちは、発想や行動を切り替えられているでしょうか。
市場の状況も踏まえると大学の財務もこの先、安泰とは言えません。現在より少ない人員で、より高度で複雑化した業務に対応することになる可能性は高いです。外部から資金を獲得する、教員や学生に対してより踏み込んだ高度な支援を行う、管理業務を最大限に効率化するといった業務は増加していくことでしょう。