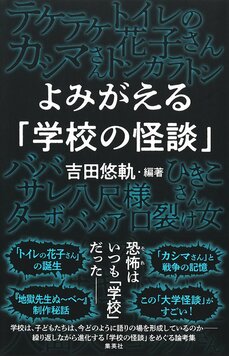学校が怪談を語る場ではなくなってきた
大槻 昔と今とでは学校そのもののイメージも大きく変わってきていますよね。学校の怪談を語ったり聞いたりすることで、実はその人が思い描いている学校のイメージが浮き彫りになることもあるんじゃないか、とこの本を読んでいて思いました。
吉田 学校の怪談というとみんな「怪談」に目を向けがちですが、「学校の」という要素も同じくらい重要です。以前は日本人の多くが「学校とはこういう空間だ」という共通認識を持っていたはずですが、今はそれが結構ばらばらになっている。小学校でも私立と公立では造りや設備が違うし、同じ公立でも地域差がある。学校とは何だという大きな問いに向き合うことになるのが、厄介でもあり楽しいところでもありました。
大槻 フリースクールや定時制の学校にも怪談はあるのかとか。あるいは学校に行かない、行けない子たちにとって学校の怪談はどんな存在なのかとか。色々知りたくなりました。
吉田 我々みたいな大人たちが、ノスタルジー込みで勝手に学校の怪談を作り上げている側面もあるかもしれない。その危うさには自覚的でありたいと思っています。
大槻 令和の学校の怪談はどうなっているんですか。
吉田 子供たちを取り巻く環境やガジェットの進化によって、もちろん変わっている部分はあります。たとえばパソコンのモニターに子供を引きずり込むAIババアがいるとか(笑)。ただそもそもの話として、学校が怪談を語る場ではなくなってきたという印象を受けます。
大槻 不謹慎だと𠮟られるんじゃないですか。昔は授業を潰して怪談をしてくれる先生が結構いたじゃないですか。僕の小学校の三、四年の担任はちょっと変わった人で、教室でギターを弾いて野坂昭如の「黒の舟唄」を歌ってくれたりね。
吉田 教室で小学生に聞かせるような歌じゃないですよね(笑)。
大槻 「男と女のあいだには~」って。その先生がよく怪談をしてくれたんです。今でも覚えていますけど、奇病にかかって全身が膿だらけになった男の話。それをわざわざ授業でするんです。後になって気づいたけど、日野日出志先生のマンガ『蔵六の奇病』の内容そのまんまだった(笑)。今だとああいう授業風景も許されないでしょうね。
吉田 問題になりますよ(笑)。今の子たちも怖い話をしていないことはないと思う。でもネットで仕入れた怪談が多いのかなという印象ですね。
大槻 そこは大きな変化ですよね。割とオカルトやホラーが好きだったんだけど、ネット時代に移行してからは全然追えなくなってしまって。「きさらぎ駅」などのネット怪談もよく知らないし、悲しいオカルト情弱になっているんです。
吉田 同じ場を共有して、体験を分かち合うというのがオカルトや怪談の楽しさではあるんですが、今はそれがネット空間とか、有料のイベントに移行している。個人がそれぞれ好きな情報にアクセスするという時代ですから、かつての口裂け女やコックリさんのような社会的ブームは起こりにくいですよね。
大槻 これは全然怪談じゃないんですが、最近の若い子たちはみんなネットで音楽を聴くっていうでしょう。TikTokとかYouTubeにあがってきた曲をランダムに再生するから、古い曲も新しい曲も区別がない。良いことではあるのかもしれないけど、「筋肉少女帯とRCサクセションはどっちが古いんですか」って言われたことがあって仰天しました。RC大先輩は六〇年代から活動してるよ! と思ったけど、筋少も八〇年代からやってるし、若い子には大差ないのかもしれない。
吉田 ある意味怖い話ですね(笑)。
大槻 最近の怪談ブームで吉田さんも引っ張りだこですが、これだけ怪談が出尽くしてもまだ新しいものは出てきますか。
吉田 画期的に新しい怪談が出てくることはそうそうないと思います。ただ「実話怪談」という概念が広まったことで、怪談を楽しむ人が増えたように、怪談を語る枠組や前提の部分は新しくなる可能性を秘めている。中身ではなくガワの部分が進化していくんじゃないでしょうか。
大槻 元からあるもののアレンジで、次の世代に受け継がれていくんですね。では学校の怪談はどうなっていくんでしょうか。
吉田 話の内容だけでなく、そもそも何を学校の怪談とするのかという前提も含めて、九〇年代に流行った学校の怪談とは違うものになっていくでしょうね。果たしてそれを学校の怪談と呼べるのか、という問題もありますし、興味は尽きませんね。