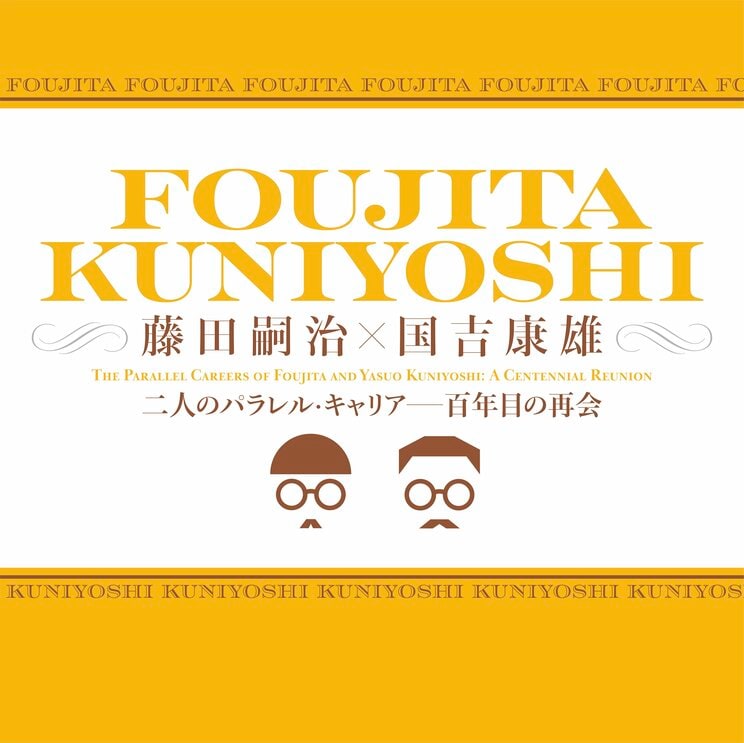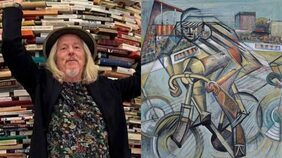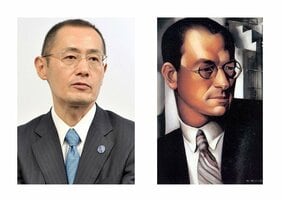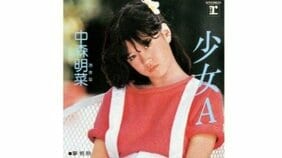「藤田嗣治三部作」から、あらたな展覧会へ
2009年秋に集英社新書より『藤田嗣治 手しごとの家』を刊行してから、早や15年以上の月日が経ちました。画家・藤田嗣治(1886-1968)の、「画家以外」の側面を紹介しようという、当時としてチャレンジングな著作は、予想以上に幅広い読者に恵まれ、その後も増刷を重ねています。
そして、2011年6月に二冊目となる『藤田嗣治 本のしごと』が出ました。春先の刊行予定が、東日本大震災の発生による物資不足もあって、数か月遅れたことを思い出します。そして、三冊目の『藤田嗣治 手紙の森へ』が2018年1月。
同年が藤田没後50年にあたり、その記念回顧展が東京都美術館と京都国立近代美術館で開かれるタイミングでした。
この展覧会はスケールをかえて、2019年初に念願のパリ巡回も果たしました(パリ日本文化会館)。同展はスポンサーにも恵まれ、日本国内に限らず、欧米、アジア圏からの作品借用がかない、この画家にとって最大規模の回顧展となりました。
作家が亡くなって半世紀、彼を看取った藤田君代夫人が亡くなって10年が経過した段階での、作家の身体の気配が薄まって、いよいよ歴史的存在へ、作品本位の評価へと移ったことを自覚しながら、監修を務めました。
思いがけず、その一年後に「パンデミック」が世界を席巻することになります。世界的な輸送網は麻痺し、一気に国際的な展覧会の開催が難しくなりました。輸送費・保険料・建材費の高騰、円安の進行、そして複数の戦争がはじまり、長期化するなかで、わたしは「つぎ」の展覧会の準備に着手しました。藤田と別の作家を組み合わせた二人展をやってみたい。
それが実現したのが、現在、兵庫県立美術館で開催中の「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア――百年目の再会」展です(2025年6月14日-8月17日)。
二人の画家、交差するキャリアと記憶
国吉康雄(1889-1953)は、藤田より三歳年少。岡山出身でアメリカに移民し、人生の大半をニューヨークで過ごした画家です。
わたしは彼の作品と美術館人としてのキャリアの初期に出会い、いつか藤田と組ませたいと思いながら、あまりに藤田研究環境の困難さに追われて四半世紀が経過してしまいました。今回、二作家の回顧展の並置ではなく、両者の特徴的な同時期の絵画を編年的に混在、対峙させることを目指しました。
パラレル(同時並行)なキャリアを示す9章構成で、パリ、ニューヨークでのデビューの1918年から国吉の没年の前年1952年までの絵画等約120点と、関連する資料(手紙、日記、写真等)から構成しました。作品は国内30館からの借用。
これまでのキャリアで、たくさんの展覧会と出版に関わってきました。集英社新書三冊では、手しごとや本、写真、日記や手紙など、「掌(たなごころ)」サイズというべき比較的小さなパーソナル・アイテムを中心に扱いました。
展覧会では扱いにくいものを、出版によって可視化する「テクニック」。今回の展覧会では、担当学芸員が国内外のアーカイブをリサーチして、相当数の資料(日記、手紙、写真)を絵画作品に紐づけしていった手法に生きています。没後半世紀以上を越えてもなお色あせない力ある作品を残した作家の力量と、手前味噌ながら、現代のキュレイション――作品・資料選定、配置、照明の共同作業で、一見異質な二人が見事に会場内で共存、共鳴しています。