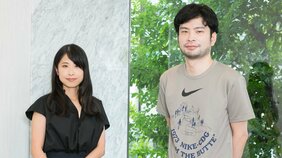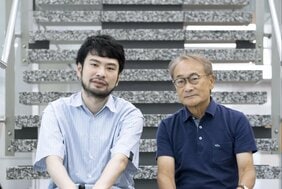大阪・関西万博を見ていると満洲感を覚える
── 満洲を題材にしたことについて、お二人とも、戦後生まれで、戦争とは遠く離れてしまっているのだけれど、離れているからこそ描ける戦争があるんじゃないか、とおっしゃっています。
門馬 これからは、戦争を知らない世代が戦争を語り継いでいくことになるので、興味を持った人が調べて人に伝えていくというのが基本となっていくのだろうなというのは、この作品を書いていて思うことです。
どうすれば満洲や戦争のことに興味を持ってもらえるように書けるかということは、すごく意識しています。
小川 読者には満洲について何も知らないという人が多いと思うのですが、そういう人からも感想が来たりしますか。
門馬 社会の授業の勉強になるとか、そう思ってもらえるのは本当にうれしいですね。ただおっしゃるように、満洲のことを何も知らない人が読んでもわかるように書かなきゃいけないので、エンタメとしてうまく食いついてもらって、興味があったら調べてみてねといった感じでつくっています。
小川 ぼくも、日本史とか世界史を読者に教えることが目的ではなくて、読んだ人が面白いと思ってくれることが一番大事だと思っています。まずは楽しんでもらって、その上で何か興味あることをこの本を通じて学んでもらえたら、それはそれでお得みたいな。
門馬 これまで満洲というのは、近代日本にとってある意味黒歴史なわけで、だから見ないように、あまり触れないようにしていたというところがあったと思いますが、戦後も八十年という時間が経過していますから、新しい目で改めて満洲を考える時期でもあるのでしょうね。
小川 今大阪・関西万博をやっていますけど、万博も一つの満洲感がありますよね。そもそも満洲自体、もともと街がなかったところを切り開いて人工的に都市をつくったわけですね。そこにいろいろな国の人が流れ込んでくる。最初はロシアが入っていって、その次に日本が開発の権利を得て発展させ、その後もさまざまな国や地域の人たちが集まってきた。いわば、当時の人たちの未来像をショーケースとして見せる都市でもあった。だから日本人も一流の建築家を送り込んで贅沢な建物をつくり、その建築はいまだに見ることができる。そういう意味で、大阪・関西万博を見ていると満洲感を覚えるんですよね。
日本も、満洲国という傀儡国家を治める大義名分としてとんでもない理想を掲げたわけですよね。それが五族協和とか王道楽土といった惹句を生み、ああいう張りぼての理想ができた。
門馬 ショーケースというのは面白いですね。ぼくも最初に阿片をテーマにしたマンガをやりませんかといわれて、どこを舞台にしようかと探して見つけたのが満洲でした。調べていくと予想以上にこの土地が面白くて、この土地自体に力をもらったという感じですね。
小川 『満州アヘンスクワッド』がマンガとして成功したことで、これまであまりマンガの題材にならなかった第二次世界大戦や満洲を扱ったいろんな作品が出るといいですよね。
門馬 そうですね。
小川 『満州アヘンスクワッド』を読んで面白かった人は、ぼくの小説を読むハードルがちょっとだけ下がると思うので、是非『地図と拳』も読んでほしいですね(笑)。