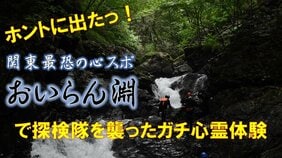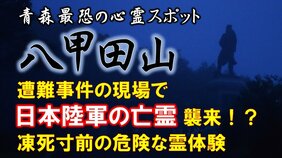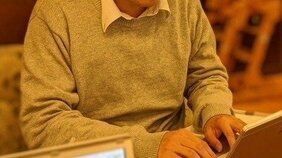後白河の無慈悲が生んだ崇徳の呪い
その後、確かにチャンスは巡ってきたのですが、崇徳が自分の子供を皇位に就けようとしたことで、朝廷は後白河天皇をそのまま維持しようという一派と、崇徳上皇の息子に跡を継がせるべきだという派に真っ二つに分かれてしまいました。
それでもこのとき、もし武士というものがいなければ、朝廷内の殴り合いで済んだかもしれないのですが、一度上皇になると、武士団を保護する立場に就くのが当時の常識でしたから、崇徳上皇の周りにはそういう人々がいました。
もちろん、後白河天皇も、鳥羽上皇の強い意志で跡を継いだ人間ですから、鳥羽上皇が保護していた武士団を使うことができました。
その結果、後白河派と崇徳派に真っ二つに分かれた朝廷の意向を受けた武士団が武力衝突し、代理戦争を始めることになってしまったのです。これが保元の乱でした。
後白河天皇は、のちに鎌倉幕府を創設した源頼朝に「日本一の大天狗」と呼ばれたほどの海千山千の男ですから、やはり戦争もうまく、平清盛と源義朝(頼朝の父)という二大勢力の長を味方につけ、争いを有利に運びました。
その結果、保元の乱は後白河天皇側が勝ち、敗れた崇徳上皇は讃岐(現在の香川県)に島流しにされ、その息子も出家させられ、天皇の相続権を失うことになりました。
このように言うと、激しい戦いの末、崇徳上皇側が敗れたように思うかもしれませんが、実際には、崇徳上皇は途中で矛を収めたのでした。そうして出家でもすれば、流罪を免れることができるのではないか、と思ったからでした。
しかし、後白河天皇は、崇徳上皇を許さず、流罪にしてしまいました。
思惑が外れた崇徳でしたが、それでも彼は配所の讃岐でおとなしく、一心に写経に務めて過ごしました。
写経というのは、読んで字のごとく、お経を書写することなのですが、これは同時にお経を読むことでもあるので、仏教に帰依し、慈悲の心を育てる行為でもあります。
そうして崇徳は、「五部大乗経」と呼ばれる膨大な経典を写し終えます。そして、この写し終えた教典を、崇徳は都の後白河のもとに送り、しかるべき寺に納めてくれるよう依頼しました。今でもそうですが、写経は基本的にお寺に納めるのが決まりだからです。
ところが後白河は、なんとその膨大なお経をそっくりそのまま讃岐の崇徳のもとに送り返したのです。
これに激怒した崇徳は、自分の右手の人差し指の先を食いちぎり、その血を使って、「この五部大乗経すべてを魔道に回向する」と言い放ちました。
さらに、天皇家を没落させ、天皇家以外の者をこの国の王にする、と呪いの言葉を発したのです。
そしてそれ以後、崇徳は髪も切らず、ひげも剃らず、爪も切らず、まさに化け物のような恐ろしい姿で天皇家を呪い続け、この世を去ったのです。
問題は、その後です。