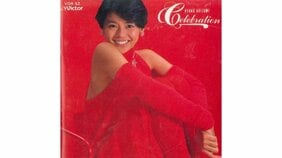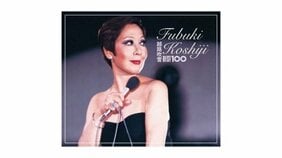日産がするべき対応策は?
そんな日産は世界に先駆けて電気自動車(EV)の量産化を進めてきた。ただ、ハイブリッド車の導入ではトヨタ(トヨタ自動車)やホンダに遅れをとった印象がある。
日産の先進技術であるe-POWERは海外でも苦戦していると言われており、このまま経営不振が続けば、日産は次世代の自動車業界の覇権争いから脱落してしまう恐れもある。
「そもそも日産は、トヨタのハイブリッド技術を後追いすることを避け、2000年代後半の時点で、ほかに類を見ない規模でEVシフトに挑戦しました。
しかし、2010年に販売開始した日産EV『リーフ』は当初の計画ほど売上が伸びず、商品展開の戦略も宙に浮いています」
一方で、テスラの成長、中国政府や欧州連合(EU)の施策により、EVシフトは2010年代後半から加速している。
「日産はその波に乗れず、またハイブリッド技術においても、自社EV技術にこだわりすぎた結果、エンジンを発電機として使うEVという位置付け(技術的にはシリーズハイブリッド)となりました。
しかし、ハイブリッドとしては結果的に中途半端な立ち位置にとどまっています。まずはこの状況を抜本的に見直すべきです。
当面は、先の会見で公表された、燃費が向上した第三世代e-POWERが対応策となるでしょう」
岐路に立たされているのは日産の主要取引先も同様だ。
2022年、日産の子会社であるカルソニックカンセイを前身とする自動車部品メーカー、マレリホールディングスが経営破綻。さらに、同社は二次破綻のリスクも報じられている。
「サプライヤーへの影響は計り知れません。肥大化した組織と、それに伴うサプライチェーンのスリム化がうまく進まず、結果的にサプライヤーの経営破綻を招いています」
また、一部では2016年に日産が三菱自動車の筆頭株主になったことが経営不振の要因とされることもあるが、桃田氏は「三菱自動車との連携自体が、今回の件に悪影響を及ぼしたとは言い切れない」とみている。
しかし、注目すべきは台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業との提携の可能性だ。すでに、鴻海は日産の筆頭株主であるルノーと協議したことが明らかになっている。
「内田社長は、マネジメントレベルでの交渉はないと断言しています。これは報道が先行している印象が強く、鴻海による日産への関与の可能性はゼロではないものの、先行きは不透明です。
ただし、ルノーが保有する日産株をどのように処理するのかについては、契約上の制約があるとも言われており、今後の展開は予測が難しい状況です」