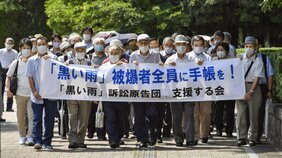残された家族を護り抜く
曽我部家は10人兄妹。勲は八男で、六男の隆二飛曹だけでなく、次男の光雄(享年29歳)と三男の秀民(同25歳)、七男の寿(同18歳)も海軍へ進み、3人全員が散華した。
長男と四男、五男は陸軍への道を選び生還している。
勲が戦時中の体験をふり返り、涙をにじませながら、こう言ったのを忘れることができない。
「隆が20(1945)年4月11日に戦死して、8日後の19日に寿が亡くなった。西条市が市葬をしてくれたのですが、うちは隆と寿の2つの箱を持って行きました。白木の箱と言っても幅、高さが15センチぐらいのボール紙の箱。
寿の箱には遺骨が入っていましたが、隆の方は『曽我部隆』と書いた紙1枚だけでした。1軒の家からいっぺんに2つの白木の箱というのは、近所では例がありませんでした。15歳のわしは寿の白木の箱を持って行きました」
勲の自宅を訪ねると、「神雷」と書かれ、日の丸が染められた鉢巻きと隆二飛曹の遺影が額に入れられ、居間に飾られていた。
「隆が茨城の鹿島で訓練をしているとき、世話になっていた下宿のおばさんから『元気で○○に行った』と手紙を貰いました。何も書いていませんでしたが、○○は鹿屋を指していたのでしょう。それに手紙には(隆は)『会わない方がいい』と言って(鹿屋に)行きましたと書いてあったそうです。
このおばさんには色々なことを話していたみたいです。本人は、兄弟が多いから、自分1人ぐらいは死んでも大丈夫だろうと思っていたみたいです。このおばさんは、遺品となる短剣と鉢巻きと歯ブラシと洗面具を送ってくれました。ところが、小包には穴が開いていて短剣だけがなかったです。誰かが取ったんでしょう」
4人の息子を戦争で失った父親の末蔵は、昭和53年に亡くなった(享年86歳)。
戦争当時50歳代だったが、息子4人が戦死したことに愚痴を言ったことはなく、気丈に振る舞っていたという。末蔵の妻は昭和13年、長女を産むと病気で亡くなった。勲が8歳の頃だ。
妻に先立たれ、4人の子供を戦争で失いながら、挫折せずにいた末蔵の苦労はいかばかりだったか、勲は言う。
「母親は乳飲み子を残して亡くなったから、父親は苦労したと思います。母親が生きていたら、気が紛れただろうに」
気丈に過ごしていた末蔵も、寄る年波か、寂しさからか、だんだんと酒の量が増え、80代になるとすっかり足腰が弱くなっていった。
戦争が終わってから33年間、「1人で耐えて生き抜いた父の気持ちを考えると、私は血の小便をしてでも家を護ろうと誓いました」と勲は言った。
文/宮本雅史