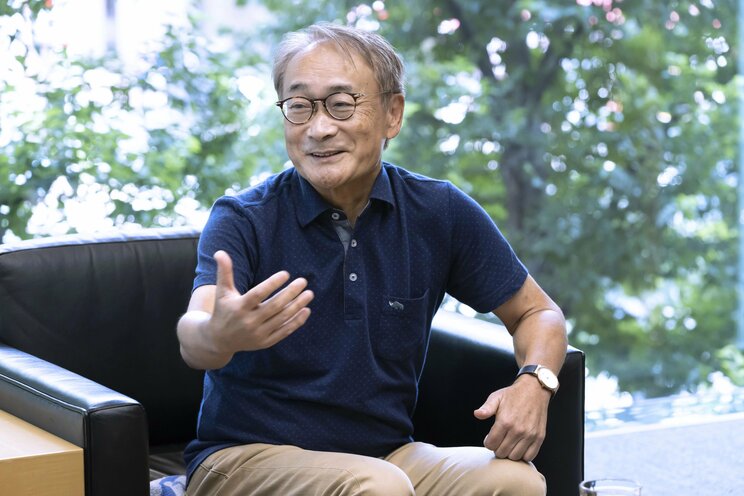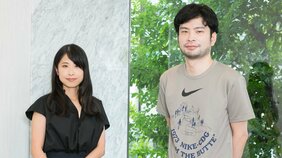dadadaのリズム
小川 実は『ゲームの王国』のときは小説の書き方がよくわかっていなくて、自分の中では破綻したというか、散らかしたものを全て片付けて終えることができなかったという感覚が残っています。だから『地図と拳』では、作品の柄が多少お行儀よくなっても、散らかしっ放しで終わらないようにしよう、破綻しないようにしようという気持ちで書き始めました。奥泉さんが『虚史のリズム』を書き始めたときとは正反対ですね(笑)。
とはいえこの作品も、終盤になるにつれ、奥泉さんの癖か美学かはわかりませんが、きちんと回収するパートが増えていきます。何といっても、dadadadadaの仕組みがあることで、はち切れそうになった小説を音楽的に収めることができてしまっているというか……。この小説のリズムは石目の語りのリズムでもあるとおっしゃっていましたが、後半になるにつれて、dadadaのリズムが前面に出てきますよね。
奥泉 後半で暴れているdadadaは、実はもともと出てくる予定はなかったんです。主人公の一人である神島が、下宿で横になっているとき、襖絵に描かれた人物が「あ」のかたちに口を開けているのに気がついて、ドイツ語の「da」と言っているのだと思った――そういうちょっとしたシーンを序盤で書いた。それだけのはずだったんです。ところが、そうか、「da」は死者が口から漏らす響きかもしれないなと、イメージがどんどん膨らんでいって……。戦争体験をどう捉えるかの問題をめぐるあれこれをこの本では繰り返し書いているわけですが、体験の全体を表象する響きとして、dadadaというダダイズムの詩句のようなフレーズが出てきた。その意味では、はち切れそうになった小説を音楽的に収めたというのはその通りで、この部分は小説テクストとしては破綻していると言えるかもしれません。
本を見てもらうと、装丁をしてくださった川名潤さんの版組が後半のほうですごいことになっているでしょう(笑)。前の方にも何度かdadadaが入っているんですが、ぶっちゃけていうと、実はそのあたりは、テクスト的に少し弱いので、なんとかdadadaで補強してくれませんかと、川名さんに頼んだんです(笑)。その意味では、失敗を辞さずというのは、ここでわずかながら実現しているのかもしれない。どちらにしても、小説というのは、公にしうる範囲内でなら何をしてもいいわけで、とりわけそういう遊びが許されるジャンルだとも思うわけで。
――dadadaのタイポグラフィで言えば、ルビにdadadaが入ってくるのは斬新だなと思いました。
奥泉 そう、そこは川名さんのアイデアですね。僕は後半でdadadaが蛇のようにうねるようにしてほしいと頼んだ(笑)。今はいくらでも奇抜なレイアウトに対応することができるじゃないですか。でも川名さんは、戦後すぐの組版でもできる範囲内でやりたい、と。そこは川名さん流のこだわりですね。
単一の物語に他者を閉じ込めない
――現実の歴史を背景に小説を書くことについて、お二人それぞれこだわりはありますか?
小川 僕が小説を書く上での一番のモチベーションになっているのは、他者について考えたいという感情なんです。もともとSFでデビューしたのも、他者のことを一番考えられるジャンルだと思ったからで……。自分とはまったく違う価値観や倫理体系を持つ人について考えたいという思いは、小説を書く上で大事にしていますね。
歴史に行き着いたのは、単純に、それまで未来に向いていた矢印が過去に向いただけです。戦前・戦中・戦後すぐ、いずれも今とはまったく違う価値観や倫理観、科学技術や社会システムのもとで生きていた人たちがいたわけで。仮に自分がその場にいたら何ができたか、どうすれば七十年以上前の戦争を自分に関係するものとして見られるか、ということを考えるのが、『地図と拳』を書く上での大きなテーマでした。
そのためにはまず、当時の人がこういう価値観のもとでこういうことを考えて生きていたという部分を描こう、と。現代の視点から眺めると、昔の人は野蛮で愚かだったという結論になってしまいがちですが、それでは近代史について考えることはできませんから。『虚史のリズム』でも、戦後の時代の価値観が示されていて、そこはすごく共感しました。
奥泉 そうですね。基本的に他者のことはわからないわけです。他人のことは究極的にはわからない。しかし人間には想像力がある。想像力を通じて他者のことを考えることができる。想像力を使って過去の人たちのことを考えられること、彼らがどのように考え行動したかを言わば共感的に描けることが、小説の最大の強みなんですよね。
ただ同時にそこには、自分が持つ単純な物語に他者を閉じ込めてしまう危険性がたえず存在しています。特攻隊が一番わかりやすい例だけど、パターンの中で「泣ける物語」を書くことはいくらでもできてしまう。でも、特攻隊をめぐる人々の思いや行動は、単純な物語では捉えられない。一方で我々はどうやっても物語的にしか世界を認識できず、他者もまた捉えることができないという難問がある。とすれば、物語そのものへの批評的な目を持つことを含め、いかなる物語でもって他者を描くべきなのか、たえず考えなくてはならない。
これには簡単な答えがあるわけではない。しかし、少なくとも言えるのは、単一の視点で他者や事象を捉えてはならないということだと思います。複数の物語をたえず用意する。いくつもの可能な物語のせめぎ合いの中で世界を構築していく作業しかないと思うんです。よく使われる言葉だと、「多層性」ということになるんだけれども。単純と言えば単純なことですが、それは何度でも言いたい。戦争にまつわる出来事は単一の物語に閉じ込められてしまう危険性が高いし、これからきっとどんどんそうなっていくんだと予感します。
小川 そうなると危険ですよね。特攻隊の感動的な話や、たとえば忠臣蔵もそうかもしれませんが、僕らの中に入ってきやすい物語化がなされています。なぜ入ってきやすいかというと、その時代に決断を下した人々の考え方や価値観を現代の僕らの視点で捉えているからだと思うんですよね。だからそうならないように、自分の物語に閉じ込めないように注意しないといけない。
奥泉 まったくそうですね。あと小川さんの小説で、方法として注目したのは、史実と虚構との関係性ですね。『地図と拳』で登場する李家鎮(リージャジェン)というのは架空の街です。加えて主要登場人物は全員フィクショナルな人物。これはひとつの方法ですよね。遠景では実在の人物も出てくるんだけど、台詞があったり内面が描かれたりする人物は、徹底してフィクショナル。僕の小説も基本的にそうなんです。今までの小説すべてそうだと言っていい。そのへんはどうですか、意識していますか。
小川 もちろん、すごく意識しています。歴史小説にはいろんな役割があって、実在の人物の再解釈もそのひとつですよね。史料にはその人の内面が描かれていないので、内面を組み立てるという仕事も小説家にはある。なぜこういう決断をしたのか、なぜこういう行動をとったのか。ただ、今のところ僕は、歴史上の人物の再解釈ではなく、近代史そのもの――もっと抽象的な、戦争って何だったんだろう、近代って何だろう、天皇って何だろうとか、そういうところ――のほうに興味があるので、再解釈ゲームには参加していません。
――『ゲームの王国』のポル・ポトは再解釈しているんじゃないですか?
小川 ポル・ポトについては、彼を扱ったフィクションがそもそも存在しないので、再解釈も何もないというか(笑)。当時、カンボジアがポル・ポトについての小説を書ける状況になくて、実際に書かれていなかったということもあるし、日本人にとってポル・ポトがすごく遠い人物だということもあります。まあ、『ゲームの王国』の中でポル・ポトはそんなに主要登場人物じゃないんですけどね。要するに、僕は別に日本の史料研究とか歴史学を前進させようとはしてないと、そういう話です。だからむしろ、実在の人物については、自分の想像力を守るために意図して出していません。出したほうが面白くなるかなと思うときもありますけど。奥泉さんはどうですか?
奥泉 いわゆる歴史小説については、書くだけの時間が今後に残されているかどうかわからないんだけれども、ひとつの課題と捉えています。日本の近代小説にその流れはあって、鴎外とか、大岡昇平とか、多くの作家が晩年に歴史小説にチャレンジしている。吉村昭さんもやっていますね。評伝というのはジャンルとして確立されていますが、それを含めて、歴史小説をどう書くのか、書けるのか、まだ掴めていなくて、やりたいんだけど、うーん、でもなあ……(笑)。「このとき甘粕はこう思った」とかって、やっぱり書きづらいじゃない。
小川 これまでフィクションにおいて、たくさんの甘粕像が描かれてきているわけですよね。半端にやると、みんなが描く甘粕とちょっとイメージが違うとか、そういうことにもなりかねないし……。
奥泉 方法論をずっと模索中なんです。
小川 「この人ってきっとこうだったんだろうな」と思える、二次創作的な妄想力がないと楽しく書けない気がします。近現代史上の人物って、「何月何日にどこにいた」「何年に昇進した」という記録がすべて残っているわけです。小説でその人物を描くとしたら、絶対に通らなければならないチェックポイントをクリアしながら、その間でひとつの人格を作っていく、解釈する、という試みになると思うんですけど、今のところ僕にはちょっと難しそうですね。できるならやってみたいですけど。
奥泉 近代史への関心と言えば、小川さんの関心の中心はどのあたりになるのかな。ポル・ポトを書いたり、満州を書いたりするのは、トータルな近代史への関心とはちょっと異なるのかなと。
小川 たぶん、もともとはユートピアに関心があるのだと思います。だから、共産党にも興味があって。うちの祖父が元共産党員でバリバリ活動していて、治安維持法か何かで逮捕されているんです。それとはあんまり関係ないのかもしれないけど、頭のいい人が集まって、「こうすれば理想の国ができるんじゃないか」と考えたことがなぜ必ず失敗するのかということは、昔から考えていますね。その問いが、満州やカンボジアを書くことにつながっているのかな。
奥泉 なるほど。僕は、とにかく太平洋戦争への関心がずっと中心にあるんです。わかりやすく言うと、どうしてああいう悲惨な戦争をしてしまったのか、そこに尽きる。でもこの関心は、小説家であることとは直接関係なくて――というのも変ですが、太平洋戦争のことを小説で書かねばならないと思っているわけではない、少なくともそれを書くために小説を書いているわけではないんです。しかしやっぱり自分の関心事だから、書くとそれが出てきてしまう。僕は太平洋戦争を中心に据えて、近代史を考えることをやってきたんですが、今回はそこから戦後のことを考えてみました。
僕の世代から見ると、戦後の占領期は謎に満ちています。むしろ戦前、戦中のほうが理解しやすい感じがある。占領期というのは、よくわからない不思議な時代なんですよね。その不思議さを小説中で表現したいという思いも、今回は特にあったんだけれども。でも繰り返しになるけれど、それは変な言い方ですが、小説の内側から出てきた関心ではなくて、もっと違うことを書いてもいいはずなんです。しかし結局は自分の関心事なので、それを書くしかないということになっちゃう(笑)。
小川 僕は一九八六年生まれなんですが、冷戦とか高度経済成長とか、自分が生まれてくる十年ぐらい前、親が学生だった頃に体験した時代が自分にとっては謎で、興味がありますね。それとちょっと似ているのかもしれません。僕の場合はむしろ、戦中や戦後のほうが理解しやすい気がします。
――奥泉さんは一九五六年生まれなので、占領期(一九四五~一九五二年)との距離感は同じくらいですね。