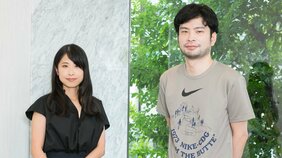小説のカルマ
奥泉 『地図と拳』は最初から義和団事件で始まって終戦までを書こうという構想だったんですか?
小川 そうです。『ゲームの王国』できれいな着地ができなかった一番の理由が、どこで終わるか決めていなかったことだったので、『地図と拳』は義和団で始めて終戦で終わろうと。始まりと終わりさえ決めておけば、だらだらすることはないだろうという感じでした。
――それで言うと、『虚史のリズム』のフィナーレは最初から決めていたんですか?
奥泉 いや、全然(笑)。殺人事件を起こすぐらいまでは考えていたけど、それだけですね。今までの長編はどれもそうだけど、ほとんどは書きながら構想も進めていく。
――今回は、これまでの作品の集大成っぽいところもあるじゃないですか。『グランド・ミステリー』と『神器』の両方の続編でもあり、さらに『雪の階』『東京自叙伝』はじめいろいろな過去作の要素が入ってきて、ラストは某作へのリンクを匂わせるという、まるでマーベル映画における『アベンジャーズ』のような(笑)。自作を全部つなげたいという欲望はあるんですか?
奥泉 たぶんあるんでしょうね(笑)。だって単純に面白いじゃない? どういう欲望なのかよくわからないけど、つい「ああ、あいつも出しておくかな」と。ちょっとした遊びみたいなものなんですけどね。特にラストなんかは、別にああいうふうじゃなくてもよかったんだけど、まあ、ああいうかたちで終わるのも面白いかなと。あと今回は、光る猫を二回出した。全部じゃないんだけど、僕の小説には光る猫がだいたい出てくるんです(笑)。ストーリーには関係ないんだけど、画家が絵の端っこにサインするみたいな感じで、光る猫を出しています。
小川 隠れミッキーみたいな。
――ミッキーと言えば、今回も鼠が大活躍しますね。
奥泉 そう。だから『東京自叙伝』にもつながっているんですよ。最後に出てくるオロチ、あれは要するに、『東京自叙伝』の地霊なんだよね、恐らく。
――それがあんなところまで出張している(笑)。
奥泉 はい(笑)。もう一度『地図と拳』の話に戻りますが、すごく大胆にひとつの架空都市、フィクショナルな街を登場させて、そこに関わる人間たちを描いていますよね。しかも、五十年ぐらいにわたる時間軸で。一種の大河小説的なテイストを狙っているんだなと思いました。
小川 そうですね。
奥泉 世代も交代していくじゃないですか。最初に読んだとき、冒頭に出て来た人物があっという間に退場して、「えっ、もう死んじゃうんだ」とびっくりしました。自分の小説だったら、あの人は最後まで生き延びますからね(笑)。そういう大河小説的な時間の流れの中で世界を構築していく書き方に、なるほど面白いなと刺激を受けました。自分もやろうかなと。僕の場合、作中の出来事のスパンがだいたい短いんですよ。
――『虚史のリズム』もこの厚さなのに、作中ではあまり時間は経っていない。
奥泉 小説内時間は四か月くらいですね。
小川 『地図と拳』で僕がイメージしていたのは、完全に『百年の孤独』なんです。
奥泉 なるほど。だから、やっぱり李家鎮という街が主役なんだ。
小川 五十年のスパンで満州を普通に書くと散漫になることはわかっていたので、ひとつの街だけに焦点を絞って、満州国をミニチュア化、カリカチュア化したものをつくるしかないなと。書いてるときは、こんなことをしていいのかとずっと心配だったんですけれども、書き終わってみたら意外と怒られませんでした(笑)。
奥泉 架空都市をつくってそれを満州の縮図とするというのは、まさしく小説ならではの技法で、面白い。べつに怒られるようなことじゃない。
――でも、近現代史の悲惨な史実を、小説ごときが恣意的に利用していいのかという議論もありますよね。
奥泉 たしかに、それはそうなんですよ。戦争をエンターテイメントにしていいのか。わかりやすい言い方をすればそういうことですよね。小説とはそういうジャンルなんだと開き直ることもできるけれども、やっぱりそこは気にすべきで、戦争の死者たちを搾取しない書き方を常に意識しますね。でも、その一方で、一種のエンターテイメント性も書き手としては考えざるを得ないわけで。それが小説というジャンルの、ある意味では怪しいところですし、逆にそこに魅力があるとも言える。
小川 背負わなきゃいけないカルマというか……。僕も搾取ということにはすごく気をつけているつもりではいますが、そういう見方で読まれてしまうことは避けられない。ただ、それでも忘却よりはましだろうと思います。つまり、誰も書かなくなって誰も論じなくなるよりは、たとえ金儲けのためだったとしても書き続けることのほうが健全じゃないか、というのが、僕の中での究極的な折り合いのつけ方ですね。傷つく人がいるから書けないという考え方ももちろんあるんだけれど、自分の中でそれと折り合いをつけながら、申し訳ないなと思いながら、でも書かないよりは書こう、と。
奥泉 そのためには結局、さっきも言った、単一の物語に人々を閉じ込めないということに尽きる。単一の視点で書いたとしても、別の物語、別の視点があり得るんだと、たえず意識して書くことが最低限のモラルだと思います。多層性こそが小説だと。ずっと同じことしか言ってないんだけどさ。
小川 あと、自分のイデオロギーのために利用しない、も大事ですかね。登場人物のイデオロギーは大切だけど、作家自身のイデオロギーのために小説を利用しない。それは作家の良心として考えていることではありますね。
“虚史”の理由
――タイトルの話に戻りますが、そもそもどうして「虚史」なんですか? 偽史でも稗史でも野史でもなく。
奥泉 正直、自分でもうまくは説明できないですね。虚史という言葉のイメージは最初からありました。「虚」というのは「フィクション(虚構)」という意味もあるけれど、「虚ろ」という意味もある。戦後という時代が虚ろなのではないかというイメージが僕の中にずっとあったんでしょうね。真面目に言えば、日本国民は太平洋戦争の死者たちをしっかり弔い得てない。その原因は、戦争体験をいまだ十分に経験化できていないということに尽きるんだけど、その結果、戦後という時代が、今僕たちが生きている時代を含めて、虚ろになっているんじゃないか、と。
――作中でもとある人物が、そもそも神国日本は負けるはずがなかった、ゆえに敗戦は現実ではない、偽の日本が負けただけだ、と主張しますね。
奥泉 そうそう、そういう思想はあり得たと思うんですよ。だから、戦争で亡くなった人たちは、いまもまだ戦場を行軍し続けているのだという強いイメージが僕にはある。彼らを無事日本に連れ戻し、しかるべき場所に落ち着いていただいたとき初めて、歴史が虚ろじゃなくなるという感覚。それは小説を書きはじめた頃からずっと一貫しているテーマですね。テーマというか、何度も言うようだけど、それを書こうと思って小説家になったわけじゃないんだけどね。そこにこだわっているのは間違いない。
――小川さんはそういうこだわりはありますか? 先ほどユートピアという話が出ましたが。
小川 そうですね。ユートピア思想の話は、何を書いていても出てくることが多いです。そもそもユートピア思想って、人類の歴史において、どの時代にもずっとあり続けているものですよね。それもあって、どの舞台で何を書いていてもそれを拾ってしまうというか……。理想の世界をつくろうとするんだけど、理屈上はうまくいくはずのものが、人間の愚かさ、人間が持つ動物的限界によって、むしろ悲惨なものになっていく。
奥泉 反転してしまう。
小川 そう、反転してしまう。それは根底にあるかもしれないですね。僕もそれが書きたくて小説を書いているわけじゃないんだけど、何を書いていてもそれが出てきてしまう。
――大東亜戦争にも、失敗したユートピア思想みたいな側面がありますね。
小川 戦争や思想って、根っこにはやはりユートピアとまでいかなくても、世界をよりよくしようという思いがあるはずです。でも、それがどこかで反転してしまうことの虚しさか、諦観か、あるいはそうじゃない可能性もあるという期待なのかわからないですけど、そこには興味を持ってしまいますね。
――『虚史のリズム』では、戦後、占領期の日本が描かれたわけですが、その先の構想はあるんですか? 『グランド・ミステリー』、『神器』、『虚史のリズム』と読んでくると、ぜひその先も読みたいという気もしますが。
奥泉 その先の戦後ね……。ちょっと、今はまだないですね。
小川 でも、書く可能性はある?
奥泉 はい。可能性は当然あります。
――では、いつかこの先が読める日が来るのを、首を長くして待ちたいと思います。今日はありがとうございました。
(2024.7.31 神保町にて)
「すばる」2024年10月号転載