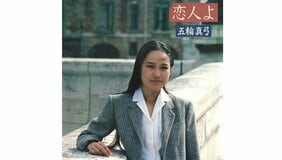権力と金の誘惑、そしてタブーへの挑戦
僕はこの本を極めてアクチュアルな「遺言」のつもりで語り下ろしている。こういう本にありがちな構成を裏切るように、まずライフワークとして追いかけている政策テーマについて、長々と述べたのは、その切迫感からだ。
二つ目に言い残したいことは、ジャーナリストの取材姿勢についてだ。
自由な言論を司るジャーナリズムは、批判力こそがその精髄だ。僕らは、誰に対しても、何に対しても、常に自由に批判できるようにしておかなければならない。
批判の矛先は権力に向けられることが多い。ということは、権力から身分と金を受け取ってはならないということになる。
田中角栄から差し出された厚さ1センチの封筒
僕はジャーナリストだけど、名刺には肩書きが一切ない。名前と連絡先だけだ。僕が好きなことを言えるのは、肩書きがないからだ。つまり、どこにも属してないので、気を遣う必要がない。
権力側の、ジャーナリストを取り込んでやろうという露骨な狙いには絶対に乗らないことだ。その一つは、政府の審議会委員というポストの提供だ。
政府は、官邸から各省庁まで数多の審議会なるものを擁していて、ジャーナリストも、メディア枠のなかで委員就任を求められることがままある。
僕もこれまで数知れず頼まれたが、すべて断った。確かに役所から情報を取れるかもしれない。だが、資料が与えられ、役所の意向に沿って報告書や答申を作るというお役所の延長のような仕事は、ジャーナリストがやることではないと思っている。
難しいのはお金だ。お金をもらうと書くべきことも書けなくなる。もちろん、原稿を書いたり、講演をしたり、司会をしたりすることに対する対価としての報酬はちゃんと受け取る。
問題は、政治の世界にはそうではない種類のお金が存在することだ。政治家が、記者なりジャーナリストなりを籠絡するために、大金を配ることがあるのだ。
他の人のことは知る由もないが、僕の体験を話しておこう。何かの役には立つかもしれない。
僕がライター時代の1980年のことだ。『文藝春秋』で田中角栄をインタビューすることになった。田中角栄は1976年にロッキード事件で逮捕、起訴されてからは、どこの取材にも一切応じていなかっただけに、このインタビューは特ダネとして注目を集めた。
なぜ、僕にその役目が回ってきたかと言うと、僕が『中央公論』に「アメリカの虎の尾を踏んだ田中角栄」という論考を書いたからだ。
「田中角栄大悪人論」だけが吹き荒れる世論に対して、ロッキード事件とは、日本の自立を構想した田中に対する米国側の謀略ではないかということを仮説として提示した。
この論考はいまでは田中評価の先鞭を付けるものとみなされているようだが、当時、僕はこの視点を、かつて共産党の幹部でその後、国際情勢分析で名を馳せた山川暁夫から学んだ。
最近、ジェレミー・ウールズィーというハーバード大学の東アジア研究科の研究者が訪ねてきて、田中角栄をめぐる当時の山川と僕の論考を読み比べたりしていることを知り、驚かされた。
彼は『中央公論』2023年6月号に「忘れられたジャーナリスト山川暁夫と『現代の眼』」という論考を発表している。