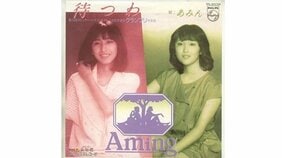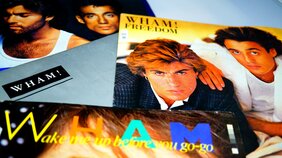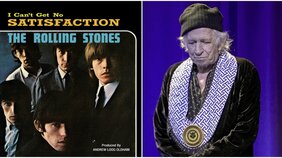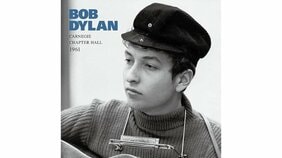追い出された人びと
アラブ‒イスラエル紛争を形づくった人口移動には、ぞっとするような対称性が見られる。
その大半が追放と逃亡によって演出されたのだ。
19世紀から20世紀初めにかけて、東欧での迫害を逃れたユダヤ人がパレスチナにやってきた。続いて、ホロコーストやホロコースト後のヨーロッパ(そこには彼らの家も未来もなくなっていた)を逃れたユダヤ人が大挙して押し寄せた。
こうした大量の人びとの移動が、1948年から49年にかけて、パレスチナのアラブ人の大々的な追放と逃亡を引き起こした。
その後、それに劣らない人数の中東のユダヤ人が、イラク、モロッコ、チュニジア、エジプトといった母国からイスラエルに逃げてきた。イスラエルの建国によって、アラブ世界における反ユダヤ主義と敵意が高まったためだ。
これらの大規模な人口移動―いまなら多くの人が民族浄化と言うだろうが―は痛ましいものだ。
元イスラエル首相のイツハク・ラビンは自らの回想録で、ベン=グリオンからこう命令されたと述べている。
1948年、アラブ人の町であるリッダ(現在はイスラエルのロッドという町で、国際空港がある)の数万人におよぶアラブ系住民を戦闘のさなかに家から追い出し、11マイル〔約18キロメートル〕先の国境の向こうのヨルダン川西岸まで歩かせるように、と(興味深いことに、この出来事は、1995年にラビンが暗殺されて以降に出版された回想録にのみ書かれている。それ以前の版では、軍の検閲によって削除されていたのだ)。
多くの場合、アラブ人の村や町は徹底的に破壊され、その住民が逃げるか追い出されるかしたのちに、基本的に地図から消し去られた。それ以外の場合、アラブ人の村の跡地にイスラエル人の新たなコミュニティが建設されることもあった。避難したアラブ人が故郷に帰ることは許されなかった。

追放の長い歴史が、特定の場所の名前の変遷を通じて、長きにわたって受け継がれている場合もある。
歴史のある一時期が消され、別の一時期が記されている現代のパリンプセスト〔もとの字句を消した上に字句を記した古代の羊皮紙〕というわけだ。
エルサレムへ続く道を見下ろす丘の上に、キブツ・パルマッハ・ツバという美しいキブツがある。1948年に破壊されたアラブ人の村の廃墟の近くに建てられたものだ。
エルサレム‒テルアビブ間の道路を通行可能にしておくための戦いの際に、ハガナの突撃部隊(パルマッハ)が戦略的な立地にあるスバ(ヘブライ語で「ツバ」または「ツォバ」)を奪取したことにちなんで名づけられた。
丘の頂上までハイキングすると、スバの廃墟を一望できる。住民が逃げ出し、戻るのを禁じられたあと、うち捨てられたままになっている。その廃墟のふもとには、十字軍のベルモント要塞の遺跡がある。
12世紀にエルサレムへ通じる西側の道を守るために建てられたものだ。ベルモントは、聖書に出てくる古代のユダヤ人村の跡地に建てられたもので、サムエル記ではこの村が、ご推察のとおりツバ〔ツォバ〕と呼ばれている。こんな具合に地名にも長い歴史が刻まれているのである。