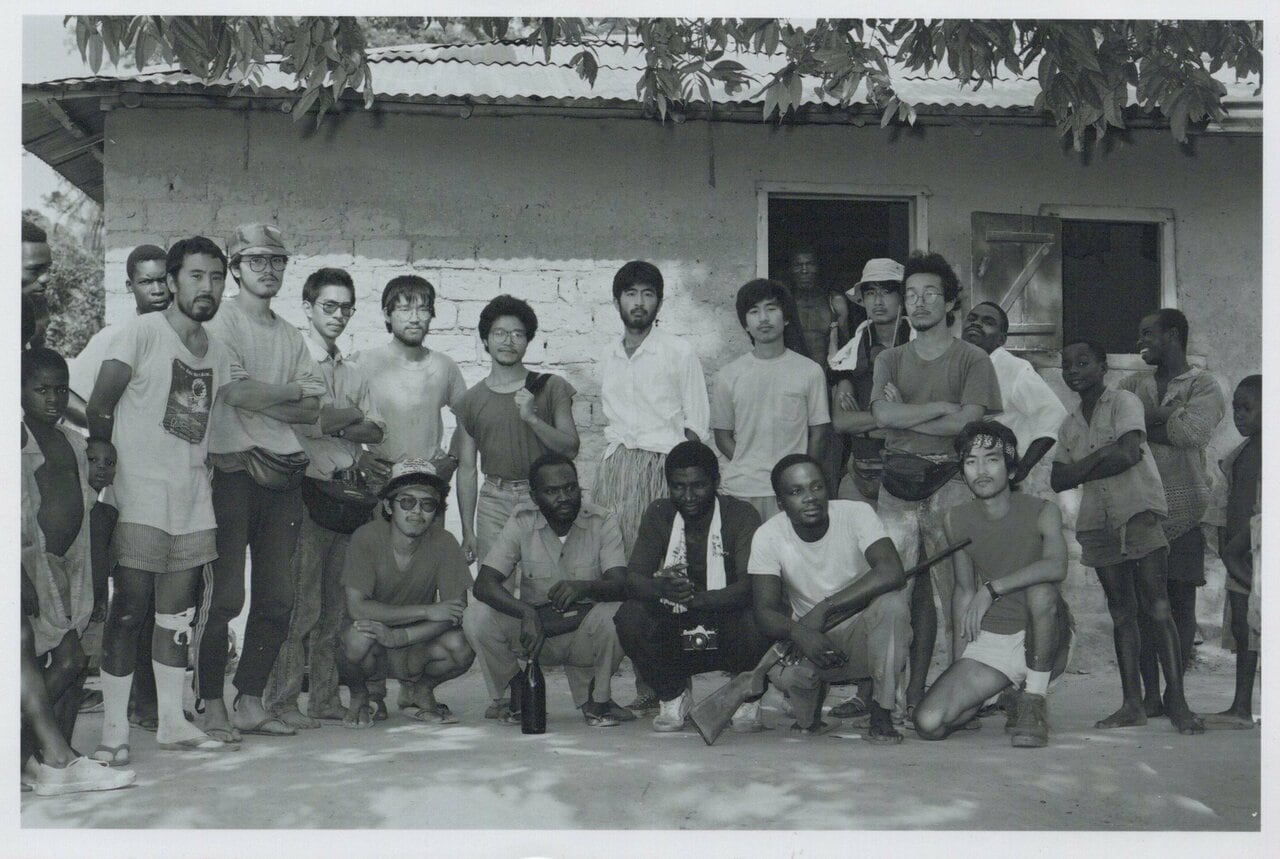脈々と受け継がれる「負の伝統」
――高野さんは1985年入部の探検部「31期生」。当時の探検部はどんな雰囲気だったんですか?
高野秀行(以下、同) かつて、探検部は一切勧誘をやらなかったんですよ。熱心に人を呼び込むこと自体がもう探検部的じゃないと思っていたらしくて。
だから入部するには部室を探して入部届を出すしかなかったんだけど、部室がすごく見つけにくい屋根裏部屋みたいな場所にあったんですね。
僕が部室を見つけたときにはもう新歓合宿が終わっていて、完全に輪に入りそびれてしまった。「何しに来たの?」みたいな感じで素っ気なくて。だから1年のときは活発に活動していませんでした。
――以降も、勧誘活動はしなかったんですか?
僕が3年のときに部員が急に減って、全員で7、8人になっちゃったんです。これはマズいと、初めて外にテーブルを出して探検部の旗を立てて、新歓ブース的なものをつくった。
だけどみんな黙って座ってるだけ。新入生が話を聞きに来ても、「なんで来たの?」みたいな。じゃあなんで勧誘のテーブル出してるんだよって、今だったらツッコみたいですけどね(笑)。

――現役部員への取材で、今も新歓ブースで「やめとけ」と入部を止められることもあるそうです。
そういう「負の伝統」っていうのは、教えてなくてもずっと引き継がれていくんですね。すごいなぁ。
――伝統というと、新入生に「探検観」を発表させ、上級生が批評を浴びせる「入部式」も当時からあったんでしょうか?
今もそんなことやってるんだ(笑)。僕らのときは、泊りがけで部の問題について議論する「1泊ミーティング」というのがありました。
そこでは必ず「探検とは何か」って話になるんですけど、全然まとまらないわけですよ。「本当の探検は宇宙か深海にしかない」っていう先輩がいれば、「裏山やそのへんにも未知がある」っていう人もいて、全く噛み合わない。