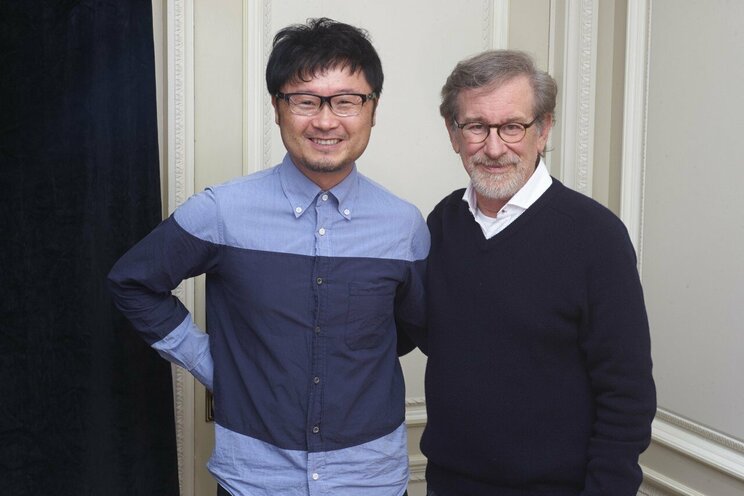毎日ビデオでも見て暮らしていたかった青春時代
折り返し地点を過ぎたと実感するようになってから、これまでの人生を振り返る機会が増えてきた。好きなアーティストや恩人に先立たれたり、思い出のモノや場所が壊されたり作り変えられてしまうなど、大切なものをなくしたことが引き金となっていて、悲しみやら後悔の念やら無力感といったありきたりの感情が伴うことになる。悲しいことに、その機会は年を重ねるごとに増えていく。
だからこそ、ウェブ上とはいえ「ロードショー」が復活したことに戸惑っている。「ロードショー」という映画情報誌と、それが与えてくれる喜びや出会いは、すでにこの世から消失したものとして気持ちの整理をつけていたからだ。長らく「洋高邦低」※と呼ばれた日本の映画市場が逆転してしまったことや、少子化や雑誌離れが重なったのだから、仕方がないーーそうあきらめるしかなかった。
※1980年~2000年代なかばまで、洋画の興収が邦画よりはるかに高い時代が続いていた状態のこと
そんな「ロードショー」がウェブのレーベルとはいえ復活した。でも、長続きする保証はどこにもないから、気を許してしまってはいけないと、浮き立つ気持ちを抑えようとしているところだ。とはいえ、2008年の休刊時にはなにも発信できていなかったので、この場を借りて心の奧にある抽斗をあけてみようと思う。

幼いころから映画好きだったぼくにとって、「ロードショー」は日常のなかにあった。少ないお小遣いでは毎号は買えなかったけれど、立ち読みや図書館で借りたりして追いかけていた。当時はインターネットなんてなかったから、はるか彼方のハリウッドと呼ばれる工場で作られるエンタメのことを知りたければ、映画情報誌を読むしかない。「ロードショー」を通じて、ぼくはその魔法に近づくことができた。
十代になると誰でも将来のことを考えはじめるようになる。でも、ぼくは行動範囲も視野も悲しいほど狭かったので、将来就きたい職業なんてなにひとつ思いつかなかった。楽しそうに仕事をしている大人を見たことがなかったし、こんな人になりたいと思えるロールモデルも存在しなかった。親戚に問われたり、進路相談のときには、その都度それらしい返答をしていたが、正直に言えば、毎日レンタルビデオを見て暮らしていたかった。