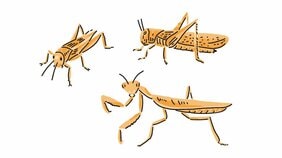棒を回転させ続け…立ち上る“甘い煙”
まずは縄が挑戦。火きり板を地面に置いて足で固定し、先ほど作った窪みに火きり棒の先端をはめる。あとは下に向かって圧力を加えながら火きり棒を回転させ、摩擦熱によって火種ができるまでそれを続けるという段取りだ。
「よっしゃあ、やるぞ〜!」
気合十分で火きり棒を回転させ始める縄。しかし、何度か回転させたところで、すぐに棒が板から外れてしまった。体勢を整えて再びチャレンジするが、2回目も3回目も同じように外れてしまう。僕もやってみたが、やはり同じ結果となった。
原因は火きり板にあるようだった。普通の板と違い、丸い枝を使っているため安定しないのだ。何度も挑戦したが、結局うまくいかないまま初日は日没を迎えてしまった。
火起こし2日目。前日の反省を踏まえ、棒を回していない方の人が火きり板を押さえることにした。さらに、疲れてきたら回す方を交代するという連携技で臨む。
縄「じゃあいくよ!」
シュッ、シュッ、シュッ、シュッ……。
縄「キツくなってきた。ごめん交代!」
文「よっしゃ任せろ!」
シュッ、シュッ、シュッ、シュッ……。
シュッ、シュッ、シュッ、シュッ……。
縄「あ、煙だ!煙が出てる!いいぞ、そのまま頑張れ!」
これまで筋疲労以外に何も生まなかった回転運動だったが、ここにきて初めて白い煙が立ち上がった。煙の匂いは不思議なことに黒砂糖のように甘くてスモーキーで、胸がドキドキする。これはうまくいくかもしれない。
火きり板は摩擦で削られ、溝から茶色い木屑がこぼれ落ちて一箇所に溜まっていく。
よし、今だ!棒の回転を止め、急いで木屑を火口に入れて息を吹きかけた。
文「フゥー、フゥー、フゥー……。消えた」
火口に入れてすぐに、煙は雲散霧消してしまった。そもそも、まだ木屑にちゃんと火種ができていなかったのだ。初めての煙で、つい焦ったのがいけなかった。しかし、確実に手応えはあった。
1人では不可能にすら思えたのに、2人で協力した途端の大きな前進。他の動物より弱かった人類が、他者と協力することで、個の能力以上のことを実現してきたという、いつかのNHKスペシャルでやっていた話は本当だった。