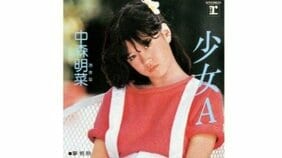豊田氏が犯したパワハラという過ち
豊田氏の行為は、間違いなくパワーハラスメントであった。
いかなる背景や事情が存在したとしても、録音された暴言や元秘書たちが証言する事実が消えることはない。陰謀があった可能性を考慮したとしても、豊田氏自身の言動が正当化されることは決してない。
99の良い行いをして、1つの悪い行いをしたからといって、1つの悪事が許されるわけではない。
豊田氏が持つ厚生労働行政に関する深い知見や、卓越した政策立案能力は疑いようのない事実である。だが、有能であるという事実が、秘書に対する人権侵害行為を帳消しにすることはない。
能力の高さと人間としての過ちは、それぞれ独立した事象として評価されるべきである。良いことは良い、悪いことは悪い、両方の事実を冷静に認識する必要がある。
一方で、逆の視点もまた重要である。99の悪い行いをして、1つだけ良い行いをしたとしても、1つの良い行いの価値が消えるものではない。
豊田氏が犯したパワハラという過ちは極めて重大である。だが、その過ちを理由に、豊田氏が持つ専門性や社会に貢献しうる能力まで、全てを否定し抹殺することが果たして社会にとって有益なのだろうか。
どのように社会と向き合い、どのように償っていくのか
過ちを犯した人間は、未来永劫、公的な活動から排除されなければならないのか。問題の本質は、過去の過ちを許すか許さないかという単純な二元論ではない。
過ちを犯した人間が、どのように反省し、どのように社会と向き合い、どのように償っていくのかというプロセスこそが問われている。
豊田氏には、過去の行為に対する批判を生涯にわたって受け止め続ける覚悟が求められる。元秘書たちの心の傷が癒えることはないかもしれない。その事実から目を背けることは許されない。
パワーハラスメントは許されざる行為である。豊田氏の過去の言動は、その一点において断罪されるべきである。この前提は揺るがない。
豊田氏が公職に復帰することに対して、強い嫌悪感や不信感を抱く人々がいるのは当然である。しかし、反省し、過ちを償おうとする人間に、社会貢献の機会を永久に与えないという社会もまた、健全とは言えないだろう。
過去の過ちが消えるものではないからと言って、将来にわたって、公的な立場に就く資格が永久に剥奪されるという結論もまた、短絡的である。
批判を真摯に受け止める責任
豊田氏には、自身が向けられる厳しい視線と批判を全て引き受けた上で、過去の自分を乗り越え、より良い社会の実現に貢献するという姿勢を行動で示し続ける責任がある。
私たち市民に求められるのは、感情的な非難に終始するのではなく、事象をありのままに受け入れ、個人が更生し社会に再び貢献するための道筋をどのように構築していくべきか、冷静に議論する覚悟である。
感情的な非難だけでなく、過ちを犯した人が社会に再び貢献するための道筋をどう作るかをよく見届けよう。
文/小倉健一