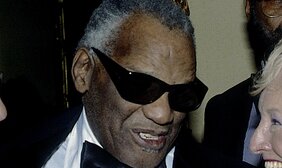今後も日本では増税が継続することになる
さきの参院選では減税を頑なに拒否する与党が負けたにもかかわらず、今後も日本では増税が継続することになる。これは何故だろうか。その秘密は実は年間の予算編成プロセスに隠れている。
政治の本質は「スケジュール」である。「何を、いつ、だれが、どのように」物事を決定していくのか、これこそが政治の全てである。
したがって、日本の予算や税制が決まるスケジュールを知れば、日本で増税が継続するか否かを知ることができる。そして、現状のスケジュールを変えることが無ければ、今後も日本の政治では増税が決定され続けることになる。
では、日本の予算や税制はどのようなスケジュールで決まっているのだろうか。
まず、例年では、日本の予算は6月に内閣府が公表する「骨太の方針」に従って、7月に財務省が概算要求基準を示し、8月末に財務省が各省からの概算要求を取りまとめ、9月~12月で財務省査定及び与党国会議員との調整が行われて、12月に政府予算案が決定され、翌年1月~3月の通常国会で予算成立という形となる。
骨太の方針で予算編成全体の方針が示されるため、財務省は骨太の方針で示された予算の特別枠(総理のわがまま)などに配慮しながら、各省から出された予算要求を取りまとめ、本予算の査定を行う流れとなっている。
そのため、一部の例外の政権を除けば、財務省がスケジュールに従って本予算の内容を統制することになる(本予算に入れることが難しかった筋悪の予算は補正予算というより緩い形でバラまかれることになる。云わば、本来は存在しなくても良い予算であり、利権向けの無駄の塊などが補正予算には凝縮されている)。
そして、本予算は翌年の通常国会に提出され、国会での審議を経て成立する。通常国会で審議スケジュールを巡って与野党が日程闘争という段取りを決められて、その流れに従って粛々と予算が成立することになる。
結局、財務省の掌の上で取りまとめられて
一方、歳出面である予算策定のスケジュールに合わせて、歳入面である税制改正のスケジュールも進むことになる。
例年の税制改正の手順は以下の通りとなっている。予算の概算要求が締め切られる8月末に、財務省(国税)・総務省(地方税)に対して各省庁や業界団体等からの税制改正要望が提出される。
この税制改正要望は財務省と各省・業界団体が調整して、税制改正の大枠が10月までに取りまとめられる。その後、財務省が取りまとめた内容をベースとして、10月~12月の間に与党税制調査会が開催される。
この与党税制調査会では、税調幹部が各省庁や業界団体に睨みを利かせながら、その要望の諾否を決定している。いわゆる業界に対するお目こぼしである租税特別措置などの利権はこの段階で正式に決定されることになる。
そして、それらが与党税制改正大綱として公表され、翌年の通常国会に同大綱を反映した税制改正法案が提出されるスケジュールとなっている。
上記のように我が国の予算や税制の大枠は、財務省の掌の上で取りまとめられて調整されている。財務省と通じて税制改正の内容や過去の経緯にあかるい政治家が「税の専門家」と呼ばれて与党税制調査会を牛耳っているが、実態としては政治が税制に関して口を出せるのは細やかな利権調整が中心である。