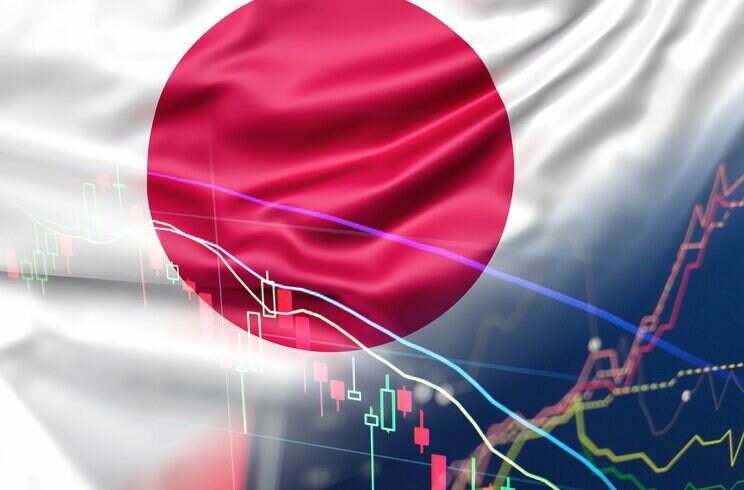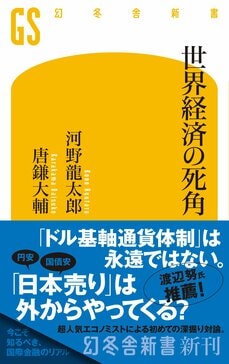貿易収支の赤字定着で、円は“別の通貨”になった
唐鎌 さらに、フローといえば、今一度、貿易収支の現在地を真摯に考えるべきだと思います。実は2013年以降、日本はヒステリックな円高が社会を混乱させ、日銀がこれに金融緩和で応戦するという局面をほとんど経験しなくなりました。
ご存じの通り、日本の経済史では円高・株安が進むと日銀が金融緩和に乗り出し、円安・株高を演出しようとするという風景が常態化していました。
河野 その風景が2013年以降に変わった。2013年といえば、異次元緩和が始まった年でもありますね。
唐鎌 おっしゃる通りです。しかし、2013年以降、日本社会があまり円高を経験しなくなったのは、異次元緩和が原因だと私は思っていません。もちろん一因ではあったと思いますが、その底流ではもっと根本的な変化が起きていました。
日本の貿易収支が趨勢的に赤字に陥ったのは、2012年以降です。貿易収支の黒字が消えたということは、東京外国為替市場における輸出企業の円買い・ドル売りが、日本全体で見れば、ほぼ消滅してしまったということでもあります。
河野 1973年の変動為替相場制移行後、日本は長く巨額の貿易収支黒字を抱えてきました。それが転換したことの意味は大きそうです。
唐鎌 おっしゃる通り、貿易収支が黒字の時代、為替市場では輸出企業を中心とする円買い・ドル売りが影響力を持ってきました。貿易収支にまつわる為替取引は、黒字であれ、赤字であれ、基本的に反対売買を伴わない「アウトライト取引」ですから、為替市場の方向感に影響を与える取引として、投資家から注目される材料です。
貿易収支が黒字であれば、円の買い切り・ドルの売り切りが多いという状況を意味するわけです。しかし、貿易収支が赤字に転じ、輸入企業による円の売り切り・ドルの買い切りが幅を利かせるようになりました。
河野 そうした「実需のフロー」のほかに、投資家を主体とする「投機のフロー」も存在するかと思います。そのバランスをどう考えればよいのでしょうか。
唐鎌 よくいただく声の一つです。「実需のフローなどは投機のフローに比べれば小さい」として、貿易収支や経常収支の分析を軽視する姿勢に私はまったく同意できません。
では「投機のフロー」は、何を基に投資判断を下すのか。それは貿易収支やこれを包含する経常収支、そして円金利や政府債務残高など、いわゆるファンダメンタルズから判断するわけです。貿易収支が黒字から赤字へ転化するという変化は、「投機のフロー」を左右するファンダメンタルズの変化に他なりません。
河野 長く経常収支は黒字のまま、ということに気を取られて、貿易収支赤字がすっかり定着していることに、つい最近まで認識が及んでいない人が少なくありませんでしたね。
唐鎌 それは非常に重要なポイントです。私は2008年10月にマーケットに入りました。
当時はリーマンショック直後だったのですが、輸出入企業に代表される東京外国為替市場のフローは、圧倒的に円買い優勢でした。でも、今はまったく逆の状況です。これはディーリングルームに身を置いている人間であれば、誰しも感じている事実のはずです。
河野 そうなのですね。
唐鎌 繰り返しになりますが、2008年当時と比べると、為替市場の景色は180度変わったと言えます。私は貿易収支の黒字が趨勢的に消滅した2012年以降、円は“別の通貨”になったと考えるべきではないかと思っています。その意味で円安は2022年から始まったわけではなく、もっと前から始まっていた現象だと思います。
河野 「新冷戦」の時代に入り、日本が米中対立の当事者となったことで、これまでのような「有事の円買い」が起こりにくくなったというだけでなく、現在の日本は貿易収支が恒常的に赤字となっており、有事になると資源価格が上昇し、その分、貿易赤字がさらに拡大する――そうした背景から、「有事の円売り」が起こっているのかもしれませんね。
文/河野龍太郎、唐鎌大輔