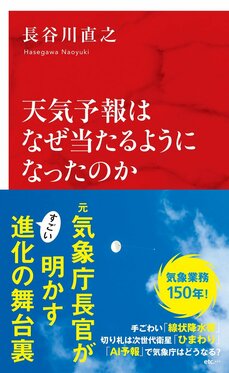オオカミ少年を防ぐために
「空振り」が増えると、だんだんその情報では人が動いてくれなくなります。羊飼いの少年が、オオカミが来たと噓をつき続けて、とうとう本当にオオカミが来たときに誰も信じてくれなかったという話と同じです。これでは情報は用をなしません。
このため、防災気象情報の基準を決めるときには、過去の気象のデータと災害のデータを集めて整理し、それを使って基準と「空振り」と「見逃し」の関係を調べ、情報の役割に照らして最適なバランスになるよう基準を決めています。
オオカミ少年のようにならないためには、「空振り」も含めて、予測の検証を行い、その結果をきちんと説明するということも大切だと思います。
オオカミ少年の話では、そもそも少年が噓をついていたということですが、「空振り」になった情報は、もちろん噓ではなく、最大限の技術と知見を駆使した結果です。
また、災害が発生したか否かという目で見れば「空振り」に見えても、ほとんど紙一重で、本当に運よく災害にならなかっただけというケースも多いのです。
気象庁では、特別警報を発表したときには、そのときの実際の大雨などの状況と、発表した情報とを比べ、その結果を公表しています。また、警報などの情報を発表した後には、関係する自治体などに、そのときの状況などを説明するようにしています。
今後もこうした取り組みを強化し、関係機関、住民などに、気象庁が全力を尽くしていることをわかってもらうことが、地域の防災を進める上で大変重要だと思います。
写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock