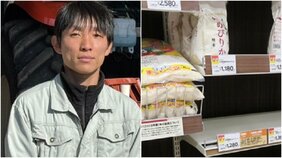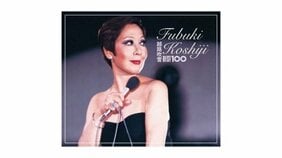価格支持型の補助金は「見せかけの自由化」に利用される危険
加えて、価格支持制度によって消費者が支払う価格が引き上げられることも明らかになっている。たとえばOECD諸国における農業生産者支援額(PSE)は、1986〜1988年に2,400億ドル、2001〜2003年でもほぼ同額で推移しており、制度的な変化が乏しいことが示されている。
さらに、価格支持型の補助金は「見せかけの自由化」に利用される危険もある。OECDの報告によれば、多くの国が名目上は補助金を削減しているが、実際には支払基準や参照価格の設定を巧妙に操作し、補助の総量を維持しているという。
これは「緑の箱」政策に名を借りた制度的詐術であり、改革を妨げる最大の要因となっている。
こうした状況を前に、小泉氏によって「改革」が実施できるのか極めて疑わしい。旧来の統制構造の中で、備蓄米の放出や食料支援の名目で市場介入を行う姿勢は、過去の自民党政権と何ら変わるところがない。
農協改革を口にしながらも、政治的対立を避けるために中途半端な調整案に終始した過去の二の舞となる可能性が高い。むしろ改革を掲げながら保護主義を温存するという「看板のすり替え」が行われる危険すらある。
農業を成長産業にしたいのであれば、必要なのは補助金の額ではなく、競争環境である。
小泉氏の本気度がまだ見えない
とくに日本のように、中間流通業者に高いマージンが集中する構造は、価格の上昇を招くだけでなく、生産者の創意工夫を削ぐ原因にもなる。
農業者が市場からの価格シグナルを正確に受け取り、それに基づいて生産判断を下せる環境がなければ、どれほど新技術や機械化が進んでも競争力は生まれない。
にもかかわらず、小泉氏からはまだ「制度の土台を壊す意志」が感じられない。農業者を保護する制度を強化しながら、表層的な言葉で改革を装うのであれば、むしろ旧態依然とした利害調整型農政を継続する意思表明に等しいことになる。
小泉進次郎氏が本気で農政を「変える」つもりで農水大臣を引き受けたのであれば、まず向き合うべきなのは、日本の農業政策がどれほど経済的にムダを生んでいるかという現実である。今の農政の仕組みは、行政が価格や生産量を操作し、市場の力を抑え込んでいる。
その結果として、競争が起こらず、生産性が上がらないまま多額の税金が費やされている。この「非効率」の問題は、単なる理屈ではない。
世界銀行が行った詳細なシミュレーション分析によって、自由な農業貿易を実現すれば、世界全体で年間約2,900億ドルもの経済的な利益が得られると試算されている。
そのうち63%もの効果は「農業にかけられた関税をなくすこと」から生まれるというのである。これは先進国、つまり日本のような国にとって大きなメリットとなる。