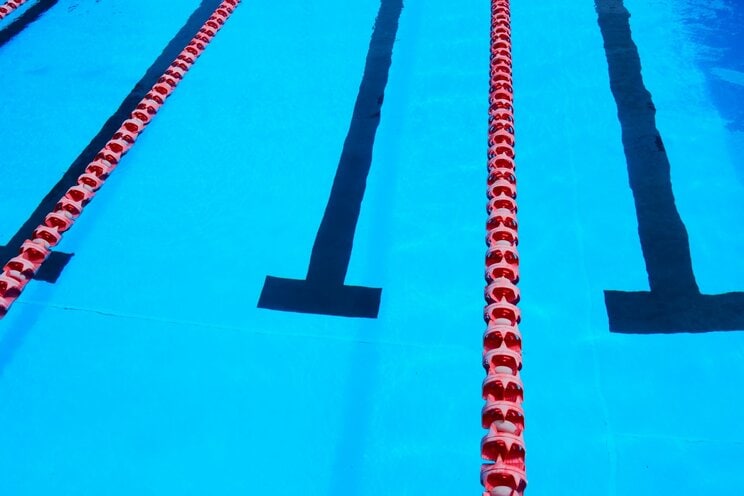「これまで通りの水泳授業を維持すること」でしか教育目的を達成できないわけではない
——そもそも日本の学校で水泳授業が広まったきっかけは何なのでしょうか。
1955年に起きた連絡船「紫雲丸」沈没事故がきっかけだと言われています。島根、広島、愛媛、高知の4つの小中学校の子どもたちが修学旅行で乗船していて、多くの命が失われました。
ちょうど同じ年に、三重県でも中学校の水泳訓練中に何十人もの生徒が亡くなる事故があり、そういうことが一気に起きたことがきっかけで、水難事故を少しでも防止するというモチベーションが働いたようです。
ほどなくして東京オリンピックが開催され、スポーツにお金を投じる動きが、水泳だけでなくさまざまな場面でかなり見られたと聞きます。その一環で、補助金でプールを作って水泳授業を推し進める動きが一気に広がりました。
——ですが、現状では本来の目的と実態がかけ離れているのでしょうか?
残念ながらそうです。教員免許を持っていることが必ずしも運動神経がいい証明ではないし、ましてや水泳指導ができる証明でもありません。中学校も保健体育の免許があり、それぞれに得意とする競技などはあるのだと思いますが、それが水泳とは限りません。
つまり、中学校の教員ならともかく、小学校の教員は必ずしも体育や水泳に関して専門性が高いとは言い切れないわけです。その中ですべての児童に指導しようと思えば、専門性の高くない教員が数人集まって水泳の授業をしている可能性もあります。
水泳が他の教科や競技と違うのは、非常に管理コストがかかり、リスクも高いという点です。誤って水を流出させてしまい、多額の損失を出してしまう事故も年に数件は起きています。
いざ事故が起きたときの重大性が他と比べてもまったく異なります。必ずしも専門性の担保されていない教員にそれだけの負荷をかけて児童生徒をリスクにさらすということは、本来の目的からかけ離れた実情にならざるを得ません。
「水の事故を防ぐ」「水に親しむ」といったことは不変の目的だとは思いますが、それが「これまで通りの水泳授業を維持すること」によってしか達成できないわけではありません。
——座学なども有用なのかもしれませんね。
台風や地震への備えとして、「こういうときは海や川に近づいてはいけない」といったことを地域ごとに学んでいきます。その地域で海や川の特性などについて学ぶことは、必ずしも実技ではなくてもいいはずです。