いけすかない女子はみんな「港区女子」
ただ、港区女子という言葉は、港区を離れて、もはや「いけすかない女性」を表すイメージとして流布しているという指摘もある。最近では、多くの人が、港区女子が実際の港区と関係がないと書いている。
前述した「港区女子小史」では、港区女子の前身として「キラキラ女子」が、ライターの小山(狂)の記事では、「セミプロ女子大生」という女性の存在が挙げられている。キラキラ女子は、インスタグラムなどを好むタイプの女性で、セミプロ女子大生はキャバクラなどで働くプロの水商売的なものを、個人で行なっていた女子大生の総称だ。どちらもある意味では「いけすかなさ」を人々に与える存在だっただろう。
それら複数のさまざまな「いけすかない」女性イメージが一つの言葉に集約されたとき、選ばれたのが「港区女子」という言葉で、「港区」だったのではないか。そこでは、港区との結び付きはもはや失われていて、ただただ「いけすかなさ」を表す言葉として、港区女子が使われる。
でも、なんで「港区」だったのだろう。
1980年代から揶揄されてきた「港区」
これを探るには、港区のイメージの変遷を追う必要がある。
端的に言って「港区」のイメージ自体が、「いけすかなさ」という言葉と共にあったのだ。
港区には昔からテレビ局などマスコミ系の会社が多く存在し、その周辺に「業界人」が多く集まっていた。中でも飯倉にある伝説のイタリアンレストラン「キャンティ」は文化人たちの交流の場になっていて、ユーミンこと松任谷由実などもここでの出会いを起点に活動を始めている。六本木に夜な夜な集まっていた人々は、「六本木族」と呼ばれて東京のセレブリティの代表的存在だった。
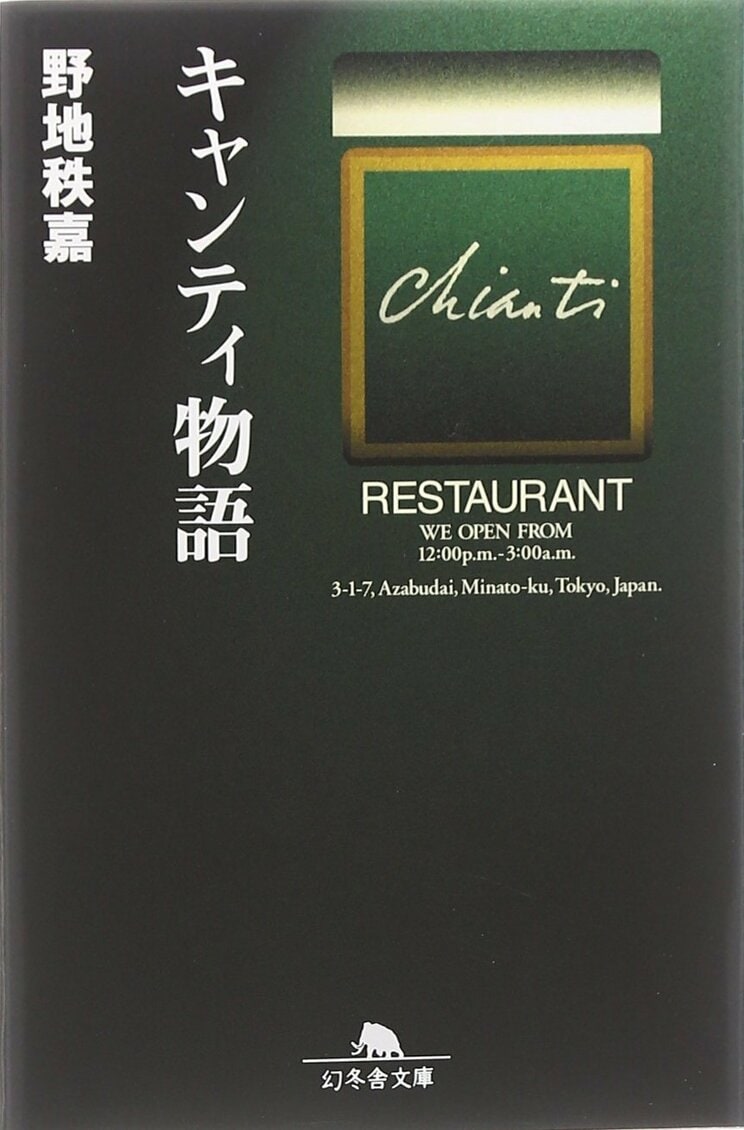
ただ、こうした港区のきらびやかな姿は、80年代から同時に揶揄の対象でもあった。1983年に出版された『見栄講座―ミーハーのための戦略と展開』という本では、港区なるものに対するイメージを垣間見ることができる(この辺りはWikipedia「港区民」という項目に詳しい)。
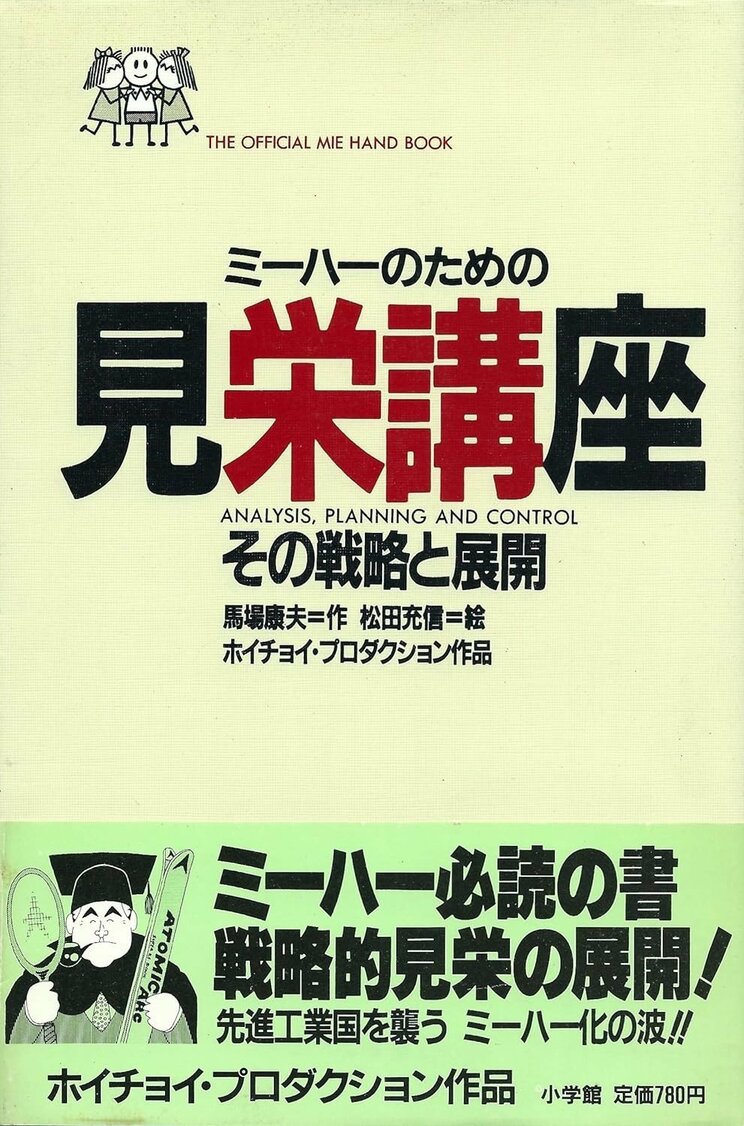
その本いわく、港区では外国人が一番偉くて、その次に港区民の日本人が位置する。最も下のヒエラルキーは港区民以外の日本人で、「外国人」を頂点とするヒエラルキーが形成されているというのだ。典型的な港区民はサングラスをつけた音楽プロデューサーや放送ディレクター。ある種の「いけすかなさ」を背景にこうした記述がなされているのだろうが、こうしたイメージは今の「港区女子」に持たれているイメージとも似たものを感じる。





























