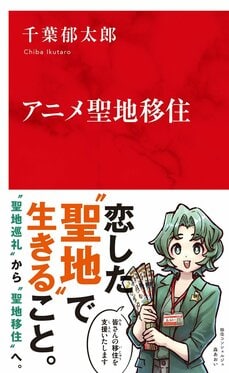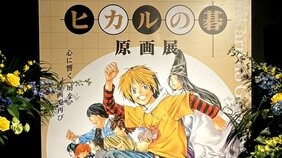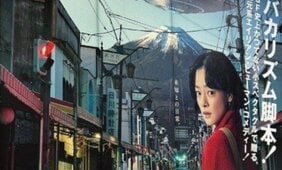地縁や血縁に代わる新しいつながり「趣味縁」
――アニメが地域活性化の一翼を担っていると。
この点は本書でも触れましたが、「聖地巡礼で経済効果〇〇億円」と経済効果を声高に宣伝することには慎重でなくてはなりません。
聖地巡礼や聖地移住が地域にどのような効果を及ぼすか、ということを考える上で、金銭や人口というハードの面だけではなく、シビックプライドやコミュニティというソフトの面に注目する必要があります。
シビックプライドは「土地に対する住民の誇り」のことで、今住んでいる街に対する人々の思いです。私の経験上、住民のシビックプライドを感じる街は「いい街だった、また来たい」と思いますが、感じない街は「もう来なくていいかな」と思ってしまいます。
聖地巡礼で地方の街を訪れると、地元民はよく「こんなところに来てもなにもないよ」と言われますが、地元民が自分の街の魅力に気付いていないことが多いのです。もちろん、気付いているうえでの単なる社交辞令かもしれませんが。
聖地巡礼・移住では、アニメに登場したスポットにとどまらず、隠れた名所や郷土史を調べ上げて地元民を驚かせるようなファンもいます。
地域活性化には「よそ者」の視点が重要だといわれますが、地元民にとっては当たり前すぎて気にもかけなかったものが、実は価値あるものだった、というのはよくある話です。
ある鷲宮の地元民が言っていたことが印象的です。これまで地元のことを「大宮から30分くらい電車で行ったところ」と説明していたのが、「あの『らき☆すた』というアニメで有名な鷲宮」で通じるようになり、自分の街にプライドを持った、とか。アニメが住民のシビックプライドを高めた好事例といえるのではないでしょうか。
コミュニティの重要性は「コミュニティはなぜ必要なのか」というそもそも論に立ち返る必要があります。
2011年は東日本大震災という未曽有の災害の年として記憶されていますが、「絆」という言葉が流行したように、人々の連帯の精神に希望を見た年でもありました。困った時はお互い様、という人々のつながりを「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)」と呼び、地域社会にとってプラスの効果をもたらすことが様々な研究で明らかになっています。
逆に現代は社会関係資本が失われ、孤独死や貧困、自暴自棄的な無差別殺人事件が社会問題になっています。コミュニティは私たちが健康かつ文化的に暮らしていくためのセーフティーネットなのです。
地方にも地縁や血縁といったコミュニティがありますが、止まらない人口減少と高齢化により急速に弱体化しています。そこでこうした地縁や血縁に代わる新しいつながりとして期待されるのが趣味を媒介としたつながりである「趣味縁」です。
「趣味縁」の例を挙げると、市民吹奏楽団やバンド、アニメファンなどが集まる同好会があります。聖地巡礼を介したファン同士のつながりや、ファンと地元民のつながりも趣味縁ということができます。
趣味縁は確かに地縁や血縁に比べると結束性が弱いものですが、出身や年齢、社会的地位という垣根を超え、人々を橋渡しする強さを持っています。
趣味縁をきっかけとした「弱いけど強い」つながりがコミュニティを作り、聖地となった地域で新しい社会関係資本を育てるきっかけになればいいなと考えています。
後編に続く