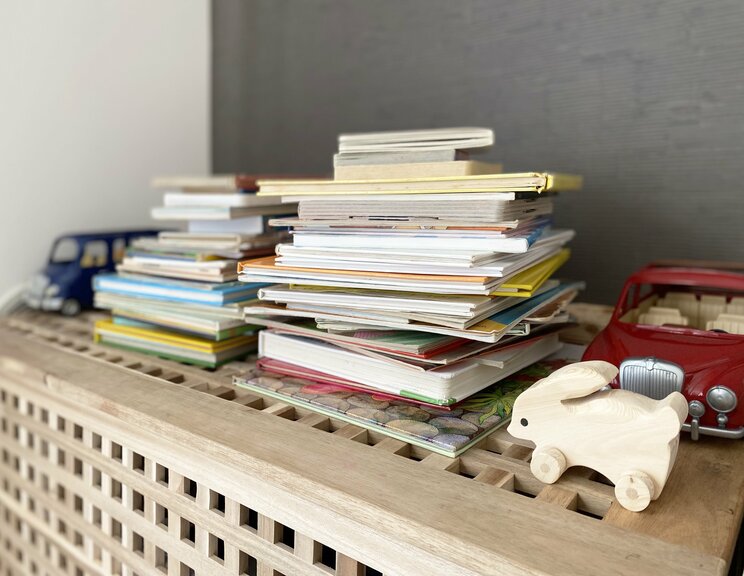保護者はどのように子の居場所を確保しているのか
居場所のない夏休みの実態が浮き彫りになったが、保護者は学童以外の居場所をどのように確保しているのか。
「うちはタワーマンションに住んでいるので、同じマンションに住む友人たちと建物内にあるスタディルームで勉強したり、1階の共有スペースで遊ぶことがほとんどです」(東京都在住、小学3年生女児の母)
「商業施設に未就学児用の無料のキッズスペースがあり、そこで妹と遊んでもらったり、フードコートでご飯を食べたり、本屋を見て回ったりしています」(埼玉県在住、未就学女児・小学2年生男児の父)
「うちは兄妹で塾に通っています。近隣で“涼しくて勉強ができるところ”をいろいろ探した結果、個別指導塾しかなかったので6月に申し込みました。ただ、運動不足が心配です」(東京都在住、小学5年生女児・中学2年生男児の母)
「たびたび利用している近所の児童館は、午前8時の開館と同時に100人近く一斉に集まります。少し離れた川崎市内では200人を超えるところもあると聞きます。日中は室内でボードゲームやブロックなどをして過ごしているようです」(神奈川県在住、小学2・4年生男児の母)
地域によっては、30〜40人程度の利用者のところもあるようだが、多くの児童館には子どもが溢れかえっている。
各自治体の取り組みは?
こうした現状に、新しい試みを始めた自治体もある。そのひとつが群馬県高崎市だ。放課後児童クラブ支援課の担当者に話を聞いた。
「富岡賢治市長の発案で、今年“放課後児童クラブ支援課”が新設され、夏休みの7月22日〜8月29日まで市役所の支所など6つの施設で小学生を預かる取り組みを始めました。
市の職員と教員を目指す大学生などと一緒に、宿題に取り組んだり、手話教室やフィンランドのスポーツ・モルックなどを楽しみます。今日は地元の信用金庫の方をお迎えし、高学年向けに金融教室を開催しました。
おかげさまで、子どもたちは非常に楽しそうですし、保護者の方からは『ここのおかげで仕事を休まなくて良くなった』と感謝の言葉をもらいました。詳細は未定ですが、来年度以降も続けていけたらと思っています」
他にも、東京都の大田区では“長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業”として、区内の集会所で夏休みの宿題や工作を子どもたちと一緒に取り組む機会を設けるなど、子どもの居場所づくりに注力している。中高生のボランティアが主体的に運営する日もあるという。