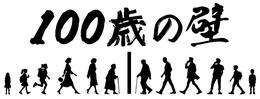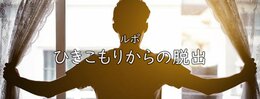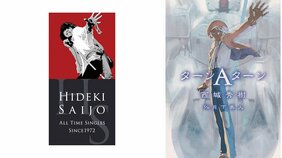外国人労働者の受け入れは経済界の要望を受けたもの
少子化により日本人の労働力が減少している上、若年層を中心とした肉体労働への忌避感が増す中、現場作業を担う外国人労働者が今後も増え続けることは間違いない。
埼玉県川口市でクルド人が解体工事業を営んでいるのも、そもそも日本人の成り手がおらず、そこに目をつけたクルド人たちが事業を請け負うようになったという事情がある。
一方、外国人労働者の増加は、参政党を躍進させた最大の要因でもある。参政党は「実質的な移民政策である特定技能制度の見直しを行い、外国人の受入れ数に制限をかける」とぶち上げ、受け入れる外国人の人数制限や日本語習得条件の厳格化といった施策を掲げる。
そもそも、外国人労働者の受け入れは経済界の要望を受けたもので、自民党長期政権下でなし崩し的に進んできた経緯がある。
特定技能制度の事実上の前身である「技能実習制度」ではこれまでに約1万人の失踪者が発生し、その一部は不法就労に就いたり、犯罪組織に加わったりといったことが社会問題になっている。
政府として「移民ではない」という態度を取り続け、本質的な問題から目を背け続けてきたことが参政党躍進の一因となったゼノフォビア(外国人嫌悪)の感情を生んだのは事実だ。
ますます日本人がマンションを買えなくなる可能性
国会の議論次第ではあるが、今後、外国人労働者の受け入れに一定の歯止めがかかる可能性がある。そうなれば、建築コストがさらに上昇し、中野サンプラザや新宿駅南口の再開発のように、建設プロジェクトが止まる事例が多発し、新規物件の供給が減ることは間違いない。
海外マネーの流入を抑えたところで、新たな物件が供給されなくなれば、価格は下落するどころか上昇し、「ますます日本人がマンションを買えなくなる可能性が高い」(全国紙経済記者)。
不動産業界における「自国民ファースト」を成功させるためには極めて絶妙なバランス感覚が不可欠だ。
例えばシンガポール政府は外資の購入規制を用意周到に準備した上で政策発表後に即実施することで抜け道を防ぎつつ、建設業の7割を占める外国人労働者は引き続き受け入れることでバランスを取っている。
翻って、我が国はどうだろうか。少数与党で求心力を失った与党と批判だけで無責任な野党が構成する国会に、我々の「住まい」の未来は託されている。
文/築地コンフィデンシャル