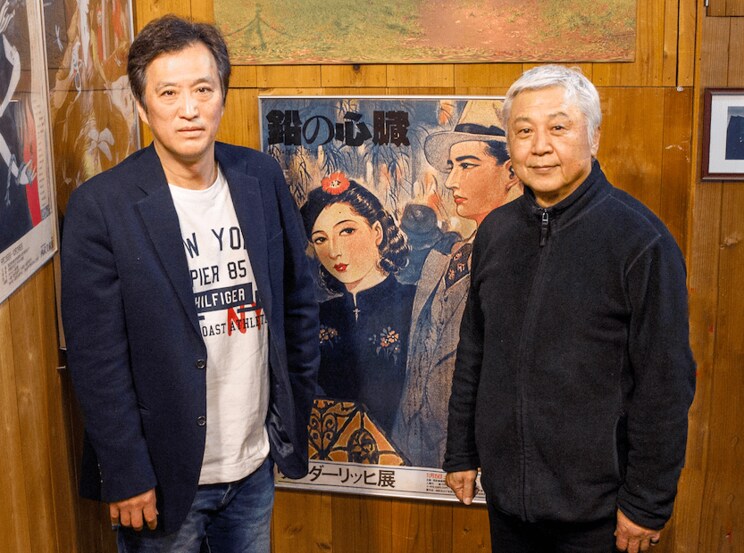
俳優、映画監督、コラムニストなど多方面で活躍する大鶴義丹氏が、ほぼ十年ぶりに上梓した小説のタイトルは『女優』。内容からも、昨年亡くなった母、女優の李麗仙氏を想い起こす読者がいるかもしれない。大鶴氏の父親である唐十郎氏が旗揚げした〈状況劇場〉にかつて在籍し、李氏とも交流が深く、唐氏の戯曲の演出に多くかかわってきた演出家・俳優・映画監督の金守珍氏が、『女優』創作の背景、演劇と舞台芸術について大鶴氏と語り合う。
構成/すばる編集部 撮影/中野義樹
女優の息子
金 いやー、面白かった。びっくりしたよ、義丹が小説家だっていうの、すっかり忘れてた。文体もしっかりしているしテンポがいいから、すぐ読めちゃった。
大鶴 本を出したのは十年ぶりなんです。
金 出だしがすごくいいよね。「有名女優の子供になることは、有名女優になることより難しい」
大鶴 確率として。女優は子どもを持たない人も多いから。
すばる文学賞でデビューしてから三十代まではなんとか小説を書いていたんですが、四十代に入ってあるとき、文字を書こうとしたら出てこない瞬間があって。そんなときに絞り出すようにして書く天才もいるでしょうけれど、僕は拗ねちゃったんです。出てくるまで書かないぞって、その後映画を作ったり他のことをしていた。でも、「すばる創刊50周年」の号に短編を書いたとき「あ、出てきた」って思って。そのころ母親が病気で倒れて、「女優」というテーマが頭に浮かんだ。「亡くなったから書いたの?」ってよく訊かれるんですけれど、そうじゃないんです。
金 僕は唐十郎が作った〈状況劇場〉に八年いたから、唐十郎と状況劇場の看板女優・李麗仙を両親として育った義丹がどんなに苦労してきたか実際に見てたし、それに二〇〇九年に放送されたNHKのドラマシリーズ「わたしが子どもだったころ」大鶴義丹編『僕は恐竜に乗らない』に僕、唐十郎役で出演もしたから、義丹の幼いころのこともなんとなく知ってはいるんだよね。妻の水嶋カンナさんが李麗仙役で。義丹の語りで進む再現ドラマ形式。今、みんなに見てほしいな。今回の小説でも女優を「恐竜の生き残り」に例えていたね。そして主人公テツロウの母親であり、大女優でもある人の名前が星崎紀李子。李麗仙の一文字が入ってる。
大鶴 作品中に出てくるベテラン天才女優・星崎紀李子がそのまま自分の母親というわけでもないんですよ。インスパイアはされていますけれど。母親よりもう少し小柄なイメージです。
金 僕は状況劇場のあと、〈新宿梁山泊〉でも李さんが倒れる寸前までずっと李さんと対峙していた。生きていれば李さんは今年八十歳になるから、唐さんが一九六九年に書いた『少女仮面』を再演する予定もあったんです。
小説『女優』の母親は七十五歳だったけれど、僕は李さんが七十三歳のときに主演に迎えて『少女仮面』を演出した。ここ新宿梁山泊の地下の劇場〈満天星〉で稽古して、下北沢の〈ザ・スズナリ〉でやった。だから、この小説、もう他人事じゃないんです。状況劇場でも李さんが一番闊達なときを見ている。老齢になられても何一つ変わらなかったな。みんな、いけにえになったかのようでした。稽古中、すっと誰か通っただけで、李さんが芝居を止めちゃうんです。「誰? 今通ったの」って。加藤亮介という、劇団の若手俳優がプロンプ(舞台演劇で、出演者が台詞などを忘れたときに合図を送る役割の人)に入ったときの話、したことあったかな?
大鶴 加藤さん、寝ちゃったんでしたっけ?
金 寝たんじゃなくて、気を失っちゃった(笑)。息をするのを忘れるくらい李さんの演技をじっと追って、酸欠になったの。「金ちゃん、この人寝てるんだけど」「ばかやろう!」って(笑)。李さんのものすごい集中力、揺るぎない強さ。女優としては日本でもトップクラスじゃないかな、義丹はその息子ですからね。
大鶴 母親もそうですが、僕、ある種の〝到達点〟に辿り着こうとする女優さんというのは、ふだんの生活が辛いんだということに気づいたんです、生い立ちから何からすべてが。女優を辞める人はたいてい芝居を続ける辛さに負けていなくなるんだけど、〝到達点〟に辿り着く人たちにとっては芝居をし続けているほうが楽なんです、ふだんの生活、人生が辛過ぎるから。努力して芝居をやっているわけじゃない。ここにいると楽よね~って(笑)。
金 「恐竜」「肉食獣」「怪獣」、この小説でも女優をいろいろに例えていたけど、僕らがとうてい入れない世界を持っている。違う空気を吸っている。
大鶴 そして、金さんもさんざん見てきていると思うんですけど、俳優としてある程度力をつけて安定してきたときに、男優はどうしても権力や覇権に向かうところがある。でも、女優はそうはならない。
金 女優は自分のためにやるんだろうね。
大鶴 シャーマン、巫女のように。
金 天から舞い降りてくる何かがあるんじゃないかな。生命体の根源にある何か。権力なんか目に入らない、自分の表現をとことん突き詰める。
小説の中で稽古して上演される芝居『娘と母の鉛筆画』で、女性の〝二面性〟が描かれているのが面白かった。芝居の主人公ツバキが実像と虚像に分裂していて、二人の役者が演じ、二人の闘いが描かれる。この視点がすごいよ。前からそういうふうに見てたの? そして一番感動したのは、二人のツバキを超えた存在としてツバキの母親がいるという構図。その母親を、この小説の主人公で演出家のテツロウの母である大女優が演じる。あれは見事だと思った。
僕は演出家だからテツロウの気持ちがとてもよくわかる。どうやったら俳優の才能を解き放つことができるか、魅力を引き出すことができるか。縛るんじゃなくて、自由にやらせる、泳がせてると、相手役によって全然変わることもある。小説の中にも、大女優が稽古に参加することによってみんなの演技が変わっていくところがあったよね。あれ、手に取るようにわかる。義丹の演出家の目が生きてると思った。
大鶴 僕は新宿梁山泊に四十一くらいのときから出入りさせてもらっています。見ていると、小劇場の女優さんというのは、大成したかたがいる一方で、女優として芽が出ない人もたくさんいる。
金 いますね。
大鶴 ここで女優という生物をたくさん見られたというのは、この小説を書く原動力にもなりました。
金 そして李麗仙という存在があって初めて書けたんだと、やっぱり僕は思うよ。実際、小説に書かれているとおりだった。
両親がまだ〈紅テント〉やっていたころなんか、義丹は嫌だったでしょうね。だって、いつも殴り合いの喧嘩ですから。いい大人たちがしょっちゅう家に来て、年がら年中宴会していて、そこで喧嘩が始まる。
大鶴 時代ですよね。本当に毎日酔っ払って殴り合って、誰かが血を流す。今だったら問題になるでしょうね。近所の人も「うるさい」って怒りに来るし、その人を劇団員が殴って警察沙汰になったこともありました。
金 さっきのNHKのドラマの中で、子供の義丹が「ギタンガ」という恐竜のおもちゃをずっと持っているんですよ、放さない。お母さんが忙しいから、劇団員の中に乳母のような存在ができる。優しいお姉さんが母親のように義丹の面倒をみたりする。その人があるとき、女優を辞めて田舎に帰っちゃう。そういうときの、心を痛める義丹の姿がうまく表現されていて……。
僕も女優が崩れ落ちていくさまをたくさん見た。年齢との闘いという部分もある。そういう意味でも、唐さんが李さんにあて書きして一番成功しているのが、『少女仮面』だと思います。李さんはかつての宝塚の大スター・春日野八千代役を初演以来、何度も演じた。中に「時はゆくゆく/乙女は婆アに、/それでも時がゆくならば、/婆アは乙女になるかしら」って老婆が歌うシーンがあります。
女性ってずっと少女なんだと思いますね。皺ができても、八十、九十になっても、紅を引くと少女に戻る。それを永遠にやり続けるのが女優さんですよね。


























