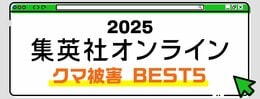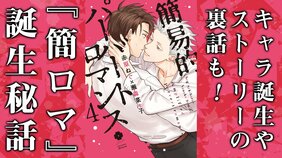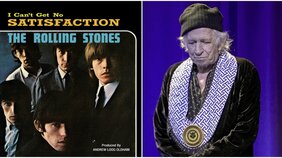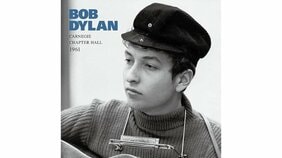人形の男色…人形がしゃべっていることがまず怖いのに
男による役者買いというと思い出すのが『男色大鑑』巻八の不気味な話です。
ある時、備前から上京した人々が、竹中吉三郎(延宝・元禄期の上方役者。若女方として評判)、藤田吉三郎(貞 享・元禄初期の京都の若女方)など、神代よりこのかた古今にまれな美少年役者五人を座敷に呼んで、春の枕を並べ、夜を徹して酒盛りをしていた。
そこへ誰からともなく箱が届けられたが、開けてもみずに放置しているうちに、若衆を迎えに駕籠が来たので、いずれもまたの約束をして、備前の人々が寝入っていたところ、箱の中から、
〝吉三ーー〟
と呼ぶ声がする。一同の中で気の強い者が蓋を取ってみると、角前髪(十五、六歳の者の半元服の髪型)の人形が入っていて、目つきといい、手足の様子といい、さながら生きた人間のよう。

よく気をつけてみると、手紙が添えてあり、
「私はこのあたりの人形屋ですが、この人形はひとしお心を込めて作り、長年看板に立てておきました。いつのころからか、この人形は魂があるように身を動かすことがたびたびとなり、しだいにわがままになっていき、近ごろは〝衆道 心〟(男色の気持ち)がついてきて、芝居帰りの太夫(若衆)たちに目をつけます。これだけでも不思議なのに、夜ごとに名指しでその子を呼びます。何となく恐ろしく、内緒で川原に流すこと二、三度になりますが、いつの間にか戻って来てしまいます。
木の端が喋ることは前代に例がなく、聞いたこともありません。我が物ながら持て余し、困っていた折も折、藤田・竹中の両太夫どのがその座におられることを見及びまして、この人形を差し上げます。後の世までの話の種に、試してごらんなさいませ」と、はっきり書いてあります。