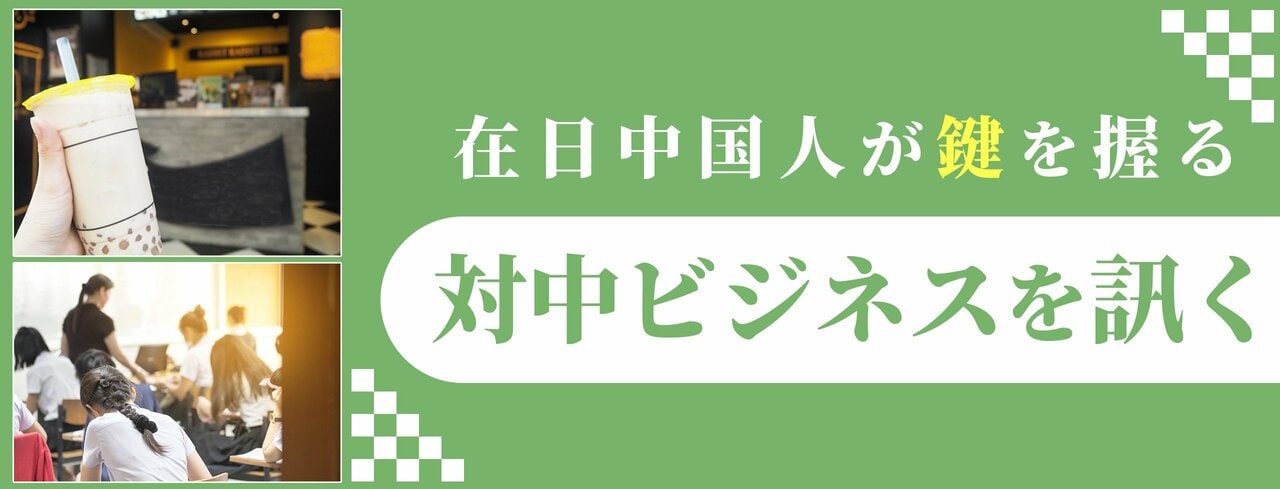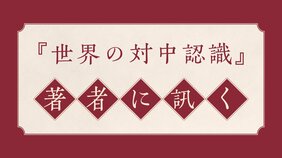在日+訪日中国人に閉じずに日本人にもトレンドが広がっていく
「永住権を取得したり帰化した人も含めて『在日中国人』と呼ぶとすると、そういう人たちが就いている仕事の代表格はIT、貿易、不動産、飲食業。それも日本内外の中国人が相手のビジネスです。たとえば日本の不動産業に関して言うなら、裕福な中国人が海外に資産を確保するため、FIRE(経済的な自立と早期リタイア)してゆっくり海外生活を送るため、あるいは投資目的で中国人に需要があり、その売買に日本在住の中国人が媒介になっている、というケースがあります」(趙氏)
また、飲食業といえば中華料理がすぐに思い浮かぶだろうが、ほかにもタピオカミルクティやチーズティなど日本でも若年層を中心に広く流行したものもあれば、螺蛳粉(ろすふん。ビーフンの一種)、海底撈火鍋、撒椒小酒館、蘭州ラーメン、ビャンビャン麺など、もともとは在日中国人やインバウンドの中国人観光客向けに日本ローカライズされていない中華料理を展開していたものが日本人にも支持されるようになったケースもある。
「越境ECやインバウンドで人気の商品を日本人が買うようになったケースもあります。たとえば肩こりに効果がある磁気ネックレスは、実は2010年前後から日本以上に中国人に爆発的に売れたことで改めて『これ、人気があるの?』と注目され、逆輸入的に日本人にも波及したと言われています」(趙氏)
つまり、在日中国人約85万人+訪日中国人約960万人(日本政府観光局調べによるコロナ禍以前の2019年データ)市場に加えて、中国人向けに展開しているビジネスから生まれたトレンドが、逆輸入のように日本人にも広がることがあるわけだ。
在日中国人によるビジネスが、チャンスはあるのに長期間・大規模になりにくい理由
こうしてみると、なかなかのビジネスチャンスがあるように思えるが、在日中国人たちは、在日+訪日中国人マーケットに関する情報をいったいどこから得ているのか。
「ビジネスに限らず、私たちのコミュニケーションツールは基本的にWeChat。中国語や中国人のLINEグループもありますが、ほとんど使いません。仕事からプライベートまで、何かあればWeChatでグループがどんどん作られてネットワークが広がり、情報共有や議論、はたまたモノの販売もしています。たとえば、日本ではなじみの薄いザリガニやカエルのような食材を使った中華料理のデリバリーを手がけている業者もいます(笑)」(趙氏)
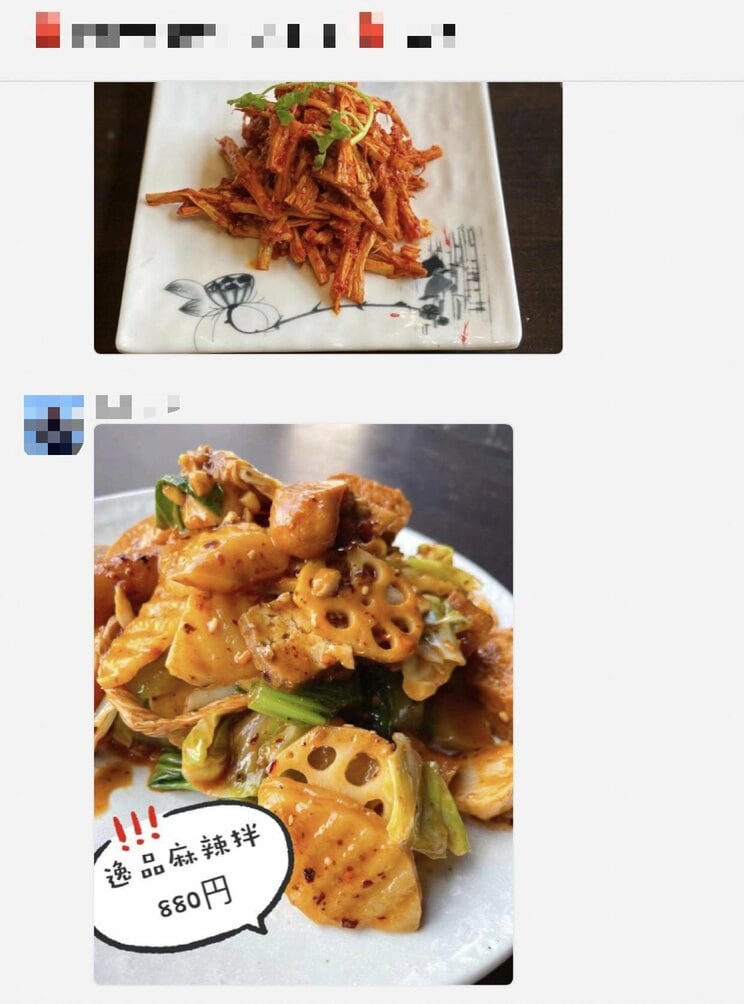
WeChatを使って中国語でやりとりすることが前提となると、そこに入っていくのは大半の日本人にとっては難しく、中国人が主に中国人向けにビジネスするサイクルが回っているだけのようにも思えるが――実は、在日中国人が手がけるビジネスは巨大になりにくい構造があり、そこに日本人や日本企業が関われるチャンスがある。
というのも永住権を持たず、帰化していない場合、在日中国人は日本で企業に勤めていたとしても、そこを辞めてしまったら、基本的には3か月で在留資格(就労ビザ)が切れてしまう。だから兼業ではできても、独立して専業で取り組める人は少ない。
また、それができたとしても小規模ECや不動産業、飲食業、個人のインフルエンサー業ではベンチャーキャピタルから投資を受けづらい。中国の投資家は日本市場のことがよくわからず、日本の投資家は在日中国人ネットワークと接点がなかったり、その先にある中国人市場のことがわからなかったりすることが多いからなおさらだ。
加えて日中関係が悪化すればモノや人の移動に制限がかかるかもしれないというカントリーリスクを懸念すると「日本と中国の情報やモノの差を利用して一気に稼ごう」と短期志向になりやすい。
「でも、本当は在日中国人と日本人、日本企業が組むことで、お互いに中長期的にビジネスを大きくできるはずなんです」(趙氏)