
歴史時代小説界の最前線で縦横無尽な執筆を続け、今年3月、「百万石の留守居役」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞した上田秀人さん。 このたび、本誌連載作『布武の果て』が単行本として刊行されることになりました。 舞台は織田信長上洛の衝撃に揺れる、大坂・堺。 有数の貿易港として自治を貫いてきた堺の商人たちが、 天下布武を期す信長との交渉を通して、「合戦ではない戦い」を繰り広げます。 商人の目から新たな信長像、そして本能寺の変の「真相」を描き出した意欲作。 その創作過程をお聞きしました。
構成/末國善己 撮影/大西二士男
信長モノの新たな挑戦
――遅ればせながら、吉川英治文庫賞のご受賞おめでとうございます。
上田 ありがとうございます。このたびようやく受賞が叶いましたが、7年連続で候補にしていただいたのは私ひとりなんじゃないかと思うんですね。昨年、6回目の候補になって落選したとき、「もう勘弁したって。恥ずかしいから」と周囲に漏らしていたんです、実は(笑)。
――本当ですか?
上田 それもあって、今回はちょうど「百万石の留守居役」シリーズが完結したタイミングでしたので、完結祝いの御祝儀なんだろうなと思って頂戴しました。まだあまり実感もないんですよね。副賞も目録でいただきましたので(笑)。
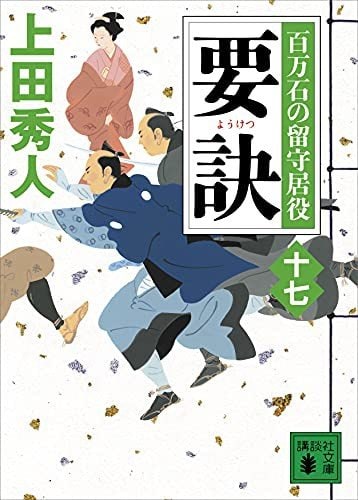
――上田さんは複数の文庫書き下ろしシリーズを同時展開させながら、今回刊行される『布武の果て』のような単行本作品も並行して手掛ける、二刀流でいらっしゃいますよね。それぞれどのような位置づけをされているのでしょうか。
上田 まず、文庫書き下ろしは言ってしまえばこぢんまりした芝居小屋なんです。読者さんが一冊にかける2時間なり3時間なり、目の前で繰り広げられるお芝居を夢中になって楽しんでいただければ、もうそれでサッと忘れられたとしても役割は全うできたと思えるといいますか。一方の単行本は、大スクリーンで観る映画のような印象です。ゆっくり読んでもらって、例えば今回の『布武の果て』なら「信長は最期、本能寺でこんなことを思ったんじゃないかなぁ……」とか、自分なりの想像や思いを巡らせながら味わっていただけたらなぁと。
――それぞれ別の楽しみ方を想定して執筆されているわけですね。今ちょうど信長の名前が出ましたが、これまでも上田さんは長編『天主信長』や短編集『本意に非ず』などで織田信長を題材として取り上げてこられました。今回も広い意味では信長モノですが、何か特別な思い入れがあったりするのでしょうか?
上田 功なり名を遂げたのに、天下人になる寸前に裏切りに遭って殺されたというその末路が好きなんですよね。いかにも日本人的な感覚かもしれませんが。あとは、史料が比較的多く残っているので物語を組み立てやすいというのもあります(笑)。『天主信長』を書くにあたって自分なりの信長像を固めるのに3、4年かかったんですが、そこから時間が経(た)ってまたさらに信長像が変化したので、それを『布武の果て』には描きました。
――今作は、堺の納屋衆・今井宗久(彦八郎)の視点で信長を描くという、面白い試みがなされていますよね。
上田 私にとってはある意味、挑戦なんです。実はデビューして間もない頃、担当編集者に「家臣から見た信長を書いてみたい」と話したら、「やめときなさい。過去、それをやろうとした作品は全部失敗してるから。第三者の目から見たヒーローを書くのは邪道です」と言われて。今回初めて信長というヒーローを脇役というか、斜め下くらいから眺めて書いてみたので、それが読者さんに受け入れられるのか、それとも編集者の言葉が正しかったことが証明されるのか、結果が楽しみでもありますね。
――そもそも、なぜ堺商人を視点人物に据えようと考えられたんでしょうか。
上田 堺には謎が多いんですよ。信長に痛い目に遭わされて謀反を起こしたりしたわけでもないのに、いつの間にか歴史から消えてしまっている。あるいは、堺商人だった千利休(宗易)が豊臣秀吉に切腹を命じられた理由もよくわかっていない。以前、「利休が秀吉に捨てられた原因は本能寺の変まで遡(さかのぼ)れるのではないか」という見立てのもとに短編(「茶人の軍略」)を書いたことがあって、それが頭に残っていたもので、今回も当初は物語の狂言回しを利休にしようかと思っていたんです。
――それがなぜ宗久メインに?
上田 利休の前半生は潰れかけた家の再建などに忙殺されて堺の交易にかかわる余裕などなかったので、物語の前半は活躍させるのが難しいなぁ、と。それで思案した結果、堺の代官として早くから第一線を張っていた今井宗久をメインに据えたという経緯です。


























