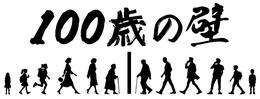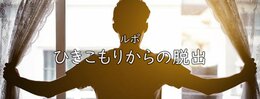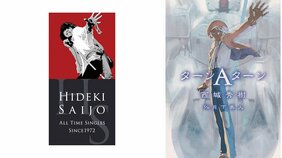令和における政治潮流と乖離していた可能性
石丸氏と「再生の道」が採用した政治的ポジショニングは、令和における政治潮流と乖離していた可能性もある。
かつての日本の憲政において、新しい政党が成功を収めるための定石とされた戦略があった。それは、右派的な自由民主党と左派的な日本社会党(及びその後継政党)との間に生じる政治的空白、すなわち中道路線を的確に捉えることであった。
1990年代の日本新党や2010年代の希望の党も、既存の左右対立に飽きた無党派層や中道志向の有権者の受け皿となることを目指した。石丸氏の戦略も、この伝統的な「第三政党」理論に酷似している。
特定のイデオロギーを強く打ち出すことを避け、具体的な政策よりも「政治不信の打破」といった抽象的なスローガンを掲げた。これは、幅広い層からの支持獲得を狙う中道戦略の一環と解釈できる。
自民党がリベラル寄りの政策を志向する傾向になった
しかし、2025年時点の日本の政治状況は、かつての中道路線が有効だった時代とは大きく異なっている。安倍晋三元首相とライバル関係にあった石破茂首相は、対中外交に力を入れる一方で、成長戦略には力を入れず、国民一人当たり2万円の給付金を検討するなど、リベラル寄りの政策を志向する傾向を見せていた。
この動きは、結果として保守的な価値観を持つ有権者層の不満を呼び起こし、政治的スペクトラムの右側に新たな空白を生み出した。SNSの普及がこの潮流を加速させている。
インターネット空間では、「愛国心」「減税」「外国人政策への懸念」「バラマキ行政への不信感」といったテーマが日々可視化され、強い共感を呼んでいる。
世界的な政治動向とも同期するこの流れは、明確な保守的、右派的メッセージを掲げる勢力にとって追い風となる。実際に、国民民主党は都議選で議席を伸ばし、保守層や無党派層の一部を取り込むことに成功した。
参政党のような新興勢力も、「日本人ファースト」といった直接的なスローガンを掲げ、国政選挙で議席を獲得している。こうした勢力は、現代の有権者が抱く不安や不満を的確に言語化し、支持を拡大している。